●製鉄諸条件の整っていた安芸広島
1江の川、太田川上流の砂鉄
2それを生む中国山地の花崗岩地層基盤
3日本一の赤松植生が炭焼きに最適
4赤松に適した雨量と気温、そして偏西風が運ぶ松の種のとどまる立地と定着最適性
6日本海渡来氏族の製鉄にも、北部九州移住者の製鉄にも最短である
7中国山地がなだらかで出雲との往来が至便
8中世以降、製鉄に関心の高い実力者毛利氏が移り住んだこと
結果的に広島市に今でもシェア100%という縫い針産業が定着した。
最古の四隅突出型墳丘墓があるのは広島県安芸、その発生から移動の歴史
●四隅突出型墳丘墓の歴史
■弥生中期後半(BC100-AD50頃)
広島県の三次盆地に発祥したという。
ここは江の川をさかのぼった中国山地の山あいに相当する。
■弥生中期後半(BC100-AD50頃)
広島県の三次盆地に発祥したという。
ここは江の川をさかのぼった中国山地の山あいに相当する。
参照
書紀 巻一 第八段 一書第一「一書曰。素戔鳴尊自天而降到於出雲簸之川上」
書紀 巻一 第八段 一書第二「一書曰。是時素戔鳴尊下到於安芸国可愛之川上也」
※安芸国の可愛川の川上とは今の江の川の上流のことであろう。出雲東部にある安来は「やすぎ」だが、「あき」から来た地名か?Kawakatu
書紀 巻一 第八段 一書第一「一書曰。素戔鳴尊自天而降到於出雲簸之川上」
書紀 巻一 第八段 一書第二「一書曰。是時素戔鳴尊下到於安芸国可愛之川上也」
※安芸国の可愛川の川上とは今の江の川の上流のことであろう。出雲東部にある安来は「やすぎ」だが、「あき」から来た地名か?Kawakatu
■弥生時代後期前半(AD50-180頃)
この時期になると日野川を下り、妻木晩田遺跡の洞ノ原2号墓を端緒にして、伯耆地方を中心に一気に分布を広げる。
規模も少しずつ大きなものが造られるようになり、突出部も急速に発達していった。
■弥生後期後半(AD180-AD250頃)
分布の中心を出雲地方に移して墳丘の一層の大型化が進むとともに、分布する範囲を北陸地方などにも広げていった。
しかし、弥生時代の終わりとともに忽然とその姿を消してしまう。
北陸では少し遅れ能登半島などで造られている。
源流は今のところ判明していないが、貼り石方形墓から発展したという可能性もある。
日本海側を中心に約90基が確認されている。
北陸地方(福井県・石川県・富山県)では現在までに計8基が知られている。」
http://houki.yonago-kodaisi.com/F-K-kohun-4sumi.html
北陸地方(福井県・石川県・富山県)では現在までに計8基が知られている。」
http://houki.yonago-kodaisi.com/F-K-kohun-4sumi.html
●安芸太田の砂鉄と広島針とたたら製鉄
「広島針の製造の歴史は、遠く300年以上前、藩主浅野家が下級武士の手内職として普及させたことに始まります。以来、品質の向上や製造の効率化などを図り地場産業として名を知られるようになりました。
「広島針の製造の歴史は、遠く300年以上前、藩主浅野家が下級武士の手内職として普及させたことに始まります。以来、品質の向上や製造の効率化などを図り地場産業として名を知られるようになりました。
広島湾に注ぐ太田川の上流50キロの中国山地の中にチューリップの針工場がある「加計」(現、安芸太田町)という地域があり、江戸時代には、中国山地の大砂鉄地帯に位置する出雲と並ぶ芸北地域の「たたら製鉄の中心地」でした。そして、太田川の水運を使って必要な物資を諸国から集めるとともに「たたら製鉄」により製造された鉄を広島に送る集積地として繁栄を極めてきました。
広島針はこのように加計の砂鉄を原料に「たたら製鉄法」によってできた鉄を太田川の水運を利用して、現在の広島市に運び、そこで針として加工することで発展してまいりました。
この鉄を独占した広島藩では、「縫針」生産の地場産業がおこり、現在でも、広島は手縫針、侍針の全国生産量の9割以上を占める我が国最大の針の産地となっております。」
http://www.tulip-japan.co.jp/hiroshima/
http://www.tulip-japan.co.jp/hiroshima/
「広島針の歴史は江戸時代に浅野藩主が長崎から針職人を連れて来たところからはじまります。広島の北部には針の材料となる鉄を「たたら」で生産する中国山地が控えていました。鉄はその中国山地から清流太田川を利用し、舟で広島へ運ばれていました。手工芸で生産されていた針はその後、機械製造へと移行するとともに品質・生産量が向上しました。「縫針」の生産量は現在も国内シェアはほぼ100%です。」
http://design-bm.shiga-irc.go.jp/collabon/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C_%E5%BA%83%E5%B3%B6%E9%87%9D-%EF%BD%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%87%9D%E3%83%BB%E3%81%8B%E3%81%8E%E9%87%9D%EF%BD%9E/
「庄原市と県境を接する島根と鳥取は、たたら製鉄を文化遺産として広域連携しているのに比べて、もうひとつの大産地であった安芸太田、北広島、安芸高田、石見は、全くそうした動きが無い」
「確か5年くらい前、著者の研究成果を雲南市でのフォーラムで拝聴したことがあり、出雲より安芸のほうが、製鉄炉の地下構造が先進的だったという話でした。」
「たたら製鉄跡の発掘調査は、戦後に始まり、島根中心に進んできたのでデータが偏り、主な産地が島根であるかのように誤解されている。で、面白いのが、戦国時代の広島の旧豊平町の発掘データと、島根のデータを比べると、明らかに安芸のほうが2世紀くらいは進んでいたということ。毛利、吉川、小早川など、安芸の勢力が拡大するのと重なるように、出雲や三原に地下構造が伝わったという事が、発掘データから読み取れます。地下構造とは、炉の地下の石組による排水口や空気口により、地面からの湿気を遮断することで、炉の温度を上げ、より量産するための当時の先端技術。何故ゆえ安芸に、独自の技術が生まれたかは解からないが、朝鮮半島の発掘調査と比べても、長四角の炉のカタチ&地下構造は日本独自のもの。たたら製鉄の考古学は、まだ途上の学問であるということらしい。」
「近年、新潟(越後)の柏崎に、海砂鉄由来の大規模な製鉄コンビナートが発見され、平安時代あたりの遺構ではないかと発掘調査されたばかり。毛利を軸とした先進的な製鉄技術は、越後との関係に由来するかもしれない。そういえば、ヤマタノオロチと高志(北陸~越後)の関係も気になるところ・・・」
http://nagareni.seesaa.net/category/10038429-1.html
●アカマツの分布も広島が日本一
アカマツ林の分布面積は、広島県が日本一!
右の図の赤い点は、日本の中のアカマツ林の分布を示した図です。九州から東北の青森県まで、全国に広く分布しています。 下の表は、県別のアカマツ林分布面積、トップ5を示したものです。なんと、広島県は、アカマツ林の分布面積は日本一なのです。
| 広島県 | 3,700 |
| 山口県 | 3,181 |
| 兵庫県 | 2,569 |
| 岡山県 | 2,060 |
| 京都府 | 1,391 |
●砂鉄を生み出す花崗岩基層
日本の花こう岩の分布
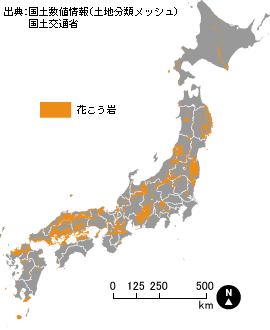
アカマツ林の分布を重ねる »
| 福島県 | 914.0 |
| 広島県 | 767.8 |
| 長野県 | 633.3 |
| 岩手県 | 594.3 |
| 岡山県 | 465.3 |
何となく、花こう岩とアカマツ林の分布が重なっているように見えます。
詳しく計算してみると、アカマツ林全体の分布量の約24%が花こう岩に成立してることがわかりました。
詳しく計算してみると、アカマツ林全体の分布量の約24%が花こう岩に成立してることがわかりました。
同上サイトから
※アカマツの中国地方の分布は、江の川・太田川流域のある広島西部(安芸国)地域と、東部の福山市海岸部(備後国)地域が二大植生地で、吉備の製鉄との関連で、以前、高温を出すことができる炭素材としてのアカマツ、その産地広島県福山市は紹介した。また花崗岩地名である阿武(あぶ)とアカマツについては
で紹介した。
■花崗岩分布と阿武地名とアカマツ植生地のリンク
以前啓上した当ブログの資料を再掲載する。
■四隅突出型型墳丘墓一覧
所在地 旧国 遺跡名 規模(m) 時期 備考
1 広島県三次市南畑敷町 備後 宗祐池西1号 10×5 IV期
2 広島県三次市南畑敷町 備後 宗祐池西2号 3.8× IV期
3 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山1号 5.2×3.5 IV期
4 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山2号 12.7×6.3 IV期
5 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山3号 6×3.6 IV期
6 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山4号 9×4.6 IV期
7 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山5号 4.5×3 IV期
8 広島県三次市大田幸町 備後 殿山38号 13×6.5 IV期
9 広島県三次市大田幸町 備後 殿山39号 未調査
10 広島県三次市東酒屋町 備後 矢谷1号 18.5×12 VI 期 長方形?
11 広島県三次市粟屋町 備後 岩脇「1号」 ?
12 広島県三次市粟屋町 備後 岩脇「2号」 ?
13 広島県庄原市宮内町 備後 佐田峠3号 15.3×8 IV期~V期-1
14 広島県庄原市高町 備後 佐田谷1号 19××14 V期-1
15 広島県庄原市山内町 備後 田尻山1号 11×9 V期-1
16 広島県北広島町南方 安芸 歳ノ神3号 10.3× V期-2
17 広島県北広島町南方 安芸 歳ノ神4号 10.2× V期-2
18 岡山県鏡野町竹田 美作 竹田8号 14× V期-1~2 ??
島根県出雲市・松江市周辺の四隅突出型型墳丘墓
19 島根県邑南町下亀谷 石見 順庵原1号 11.5×9 V期-2
20 島根県隠岐の島町西町 隠岐 大城 18×11 V期-3~VI 期-1
21 島根県出雲市大津町 出雲 西谷1号 V期-3
22 島根県出雲市大津町 出雲 西谷2号 35×24 V期-3
23 島根県出雲市大津町 出雲 西谷3号 40×30 V期-3
24 島根県出雲市大津町 出雲 西谷4号 32×26 V期-3
25 島根県出雲市大津町 出雲 西谷6号 17× VI 期
26 島根県出雲市大津町 出雲 西谷9号 43×33 VI 期
27 島根県出雲市中野町 出雲 中野美保1号 11×9.5 V期-3
28 島根県出雲市東林木町 出雲 青木1号 14×10? V期-3
29 島根県出雲市東林木町 出雲 青木2号 9× VI 期
30 島根県出雲市東林木町 出雲 青木3号
31 島根県出雲市東林木町 出雲 青木4号 17× IV期?
32 島根県松江市鹿島町 出雲 南講武小廻 VI 期 ?
33 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ1号 10.7×7.4 V期-3
34 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ2号 4.5以上× V期-3
35 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ3号 3以上×
36 島根県松江市浜乃木町 出雲 友田 12× V期-1? ?
37 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前1号 7.1×6.2
38 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前2号 11以上×8以上 V期-3 ?
39 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前3号 18×12
40 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前4号 7× ?
41 島根県松江市矢田町 出雲 来美 10×8 V期-3
42 島根県松江市矢田町 出雲 間内越1号 8.8×6.7 VI 期
43 島根県松江市矢田町 出雲 間内越4号 16.5×9.7 V期-3 ?
44 島根県松江市八幡町 出雲 的場 13以上× V期-3 ?
45 島根県松江市坂本町 出雲 沢下5号 7×6 V期-3~VI 期-1
46 島根県松江市坂本町 出雲 沢下6号 12×11 V期-3~VI 期-1
47 島根県東出雲町出雲郷 出雲 大木権現山1号 23×12 VI 期-2 ?
島根県安来市周辺の四隅突出型型墳丘墓
48 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺8号 18×14 未調査
49 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺9号 19×16 V期-3
50 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺10号 19×19 V期-3
51 島根県安来市西赤江町 出雲 宮山IV号 19×15 VI 期-2
52 島根県安来市西赤江町 出雲 安養寺1号 20×16 VI 期-2
53 島根県安来市西赤江町 出雲 安養寺3号 30×20
54 島根県安来市久白町 出雲 塩津山6号 29×26 未調査
55 島根県安来市久白町 出雲 塩津山10号 34×26 未調査
56 島根県安来市西赤江町 出雲 下山 20×17 VI 期? 未調査
57 島根県安来市伯太町 出雲 カウカツE-1の1号 11×7 V期-3
鳥取県西部(米子市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
58 鳥取県米子市尾高 伯耆 尾高浅山1号 10×7 V期-1
59 鳥取県米子市日下 伯耆 日下1号 10×7 V期-2
60 鳥取県伯耆町父原 伯耆 父原1号 12× VI 期-2
61 鳥取県伯耆町父原 伯耆 父原2号 9.5×6 VI 期-2 貼石なし
62 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原1号 6.5×5.4 V期-1
63 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原3号 4.2×3.9 V期-1
64 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原4号 4.3×3.6 V期-1
65 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原5号 2.1×2.0
66 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原7号 4.4×4.0 V期-1
67 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原8号 4.9×4.4 V期-1
68 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原9号 2.0×1.1 V期-1 墓上施設か
69 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原10号 2.0×1.6 墓上施設か
70 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原11号 1.6×1.3 墓上施設か
71 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原12号 1.3×1.2 墓上施設か
72 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原13号 1.4×1.3 墓上施設か
73 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原16号 1.5× ?墓上施設か
74 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原17号 1.5×1.3 ?墓上施設か
75 鳥取県大山町富岡 伯耆 仙谷1号 13×13? V期-2
76 鳥取県大山町富岡 伯耆 仙谷2号 7.4×7.1 V期-2
77 鳥取県大山町長田 伯耆 徳楽 19×19 VI 期-2 未調査
鳥取県中部(倉吉市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
78 鳥取県倉吉市上神 伯耆 柴栗 V期-2 ?
79 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺1号 14× V期-2
80 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺2号 6× V期-2
81 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺3号 6× V期-2
82 鳥取県倉吉市山根 伯耆 藤和 10×8.5
83 鳥取県湯梨浜町宮内 伯耆 宮内1号 17× V期-2
鳥取県東部(鳥取市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
84 鳥取県鳥取市桂見 因幡 西桂見 40以上× V期-3
85 鳥取県鳥取市国府町 因幡 糸谷1号 14×12 VI 期-2
兵庫県の四隅突出型型墳丘墓
86 兵庫県加西市網引町 播磨 周遍寺山1号 9.5×6 ??
87 兵庫県小野市船木町 播磨 船木南山 14× V期? ??
北陸・東北地方の四隅突出型型墳丘墓
88 福井県福井市清水町 越前 小羽山30号 26×22 V期-3 貼石なし
89 福井県福井市清水町 越前 小羽山33号 7×5 V期-3 ?貼石なし
90 福井県福井市高柳町 越前 高柳2号 6.2×5.5 VI 期-1 貼石なし
91 石川県白山市一塚町 加賀 一塚21号 18×18 VI 期-1 貼石なし
92 富山県富山市婦中町 越中 富崎1号 20×20 VI 期-2 貼石なし
93 富山県富山市婦中町 越中 富崎2号 20×20 VI 期-2 貼石なし
94 富山県富山市婦中町 越中 富崎3号 22×21 V期-3 貼石なし
95 富山県富山市婦中町 越中 六治古塚 24.5× VI 期-2 貼石なし
96 富山県富山市婦中町 越中 鏡坂1号 24.1× VI 期-1 貼石なし
97 富山県富山市婦中町 越中 鏡坂2号 13.7× VI 期-1 貼石なし
98 富山県富山市杉谷 越中 杉谷4号 25×25 VI期-2 貼石なし
99 富山県富山市古沢 越中 呉羽山丘陵No6 19×19 未調査
100 富山県富山市古沢 越中 呉羽山丘陵No10 23.5×22 未調査
101 富山県富山市金屋 越中 呉羽山丘陵No18 25×23 未調査
102 福島県喜多方市塩川町 石背 舘ノ内1号周溝墓 9×8 弥生末~古墳初 四隅突出型方形周溝墓
103 福島県喜多方市塩川町 石背 荒屋敷4号遺構 12× 弥生末~古墳初 四隅突出型方形周溝墓
資料 http://houki.yonago-kodaisi.com/zu-4sumi-1.jpg
所在地 旧国 遺跡名 規模(m) 時期 備考
1 広島県三次市南畑敷町 備後 宗祐池西1号 10×5 IV期
2 広島県三次市南畑敷町 備後 宗祐池西2号 3.8× IV期
3 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山1号 5.2×3.5 IV期
4 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山2号 12.7×6.3 IV期
5 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山3号 6×3.6 IV期
6 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山4号 9×4.6 IV期
7 広島県三次市四拾貫町 備後 陣山5号 4.5×3 IV期
8 広島県三次市大田幸町 備後 殿山38号 13×6.5 IV期
9 広島県三次市大田幸町 備後 殿山39号 未調査
10 広島県三次市東酒屋町 備後 矢谷1号 18.5×12 VI 期 長方形?
11 広島県三次市粟屋町 備後 岩脇「1号」 ?
12 広島県三次市粟屋町 備後 岩脇「2号」 ?
13 広島県庄原市宮内町 備後 佐田峠3号 15.3×8 IV期~V期-1
14 広島県庄原市高町 備後 佐田谷1号 19××14 V期-1
15 広島県庄原市山内町 備後 田尻山1号 11×9 V期-1
16 広島県北広島町南方 安芸 歳ノ神3号 10.3× V期-2
17 広島県北広島町南方 安芸 歳ノ神4号 10.2× V期-2
18 岡山県鏡野町竹田 美作 竹田8号 14× V期-1~2 ??
島根県出雲市・松江市周辺の四隅突出型型墳丘墓
19 島根県邑南町下亀谷 石見 順庵原1号 11.5×9 V期-2
20 島根県隠岐の島町西町 隠岐 大城 18×11 V期-3~VI 期-1
21 島根県出雲市大津町 出雲 西谷1号 V期-3
22 島根県出雲市大津町 出雲 西谷2号 35×24 V期-3
23 島根県出雲市大津町 出雲 西谷3号 40×30 V期-3
24 島根県出雲市大津町 出雲 西谷4号 32×26 V期-3
25 島根県出雲市大津町 出雲 西谷6号 17× VI 期
26 島根県出雲市大津町 出雲 西谷9号 43×33 VI 期
27 島根県出雲市中野町 出雲 中野美保1号 11×9.5 V期-3
28 島根県出雲市東林木町 出雲 青木1号 14×10? V期-3
29 島根県出雲市東林木町 出雲 青木2号 9× VI 期
30 島根県出雲市東林木町 出雲 青木3号
31 島根県出雲市東林木町 出雲 青木4号 17× IV期?
32 島根県松江市鹿島町 出雲 南講武小廻 VI 期 ?
33 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ1号 10.7×7.4 V期-3
34 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ2号 4.5以上× V期-3
35 島根県松江市玉湯町 出雲 大谷Ⅲ3号 3以上×
36 島根県松江市浜乃木町 出雲 友田 12× V期-1? ?
37 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前1号 7.1×6.2
38 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前2号 11以上×8以上 V期-3 ?
39 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前3号 18×12
40 島根県松江市西津田町 出雲 東城ノ前4号 7× ?
41 島根県松江市矢田町 出雲 来美 10×8 V期-3
42 島根県松江市矢田町 出雲 間内越1号 8.8×6.7 VI 期
43 島根県松江市矢田町 出雲 間内越4号 16.5×9.7 V期-3 ?
44 島根県松江市八幡町 出雲 的場 13以上× V期-3 ?
45 島根県松江市坂本町 出雲 沢下5号 7×6 V期-3~VI 期-1
46 島根県松江市坂本町 出雲 沢下6号 12×11 V期-3~VI 期-1
47 島根県東出雲町出雲郷 出雲 大木権現山1号 23×12 VI 期-2 ?
島根県安来市周辺の四隅突出型型墳丘墓
48 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺8号 18×14 未調査
49 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺9号 19×16 V期-3
50 島根県安来市西赤江町 出雲 仲仙寺10号 19×19 V期-3
51 島根県安来市西赤江町 出雲 宮山IV号 19×15 VI 期-2
52 島根県安来市西赤江町 出雲 安養寺1号 20×16 VI 期-2
53 島根県安来市西赤江町 出雲 安養寺3号 30×20
54 島根県安来市久白町 出雲 塩津山6号 29×26 未調査
55 島根県安来市久白町 出雲 塩津山10号 34×26 未調査
56 島根県安来市西赤江町 出雲 下山 20×17 VI 期? 未調査
57 島根県安来市伯太町 出雲 カウカツE-1の1号 11×7 V期-3
鳥取県西部(米子市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
58 鳥取県米子市尾高 伯耆 尾高浅山1号 10×7 V期-1
59 鳥取県米子市日下 伯耆 日下1号 10×7 V期-2
60 鳥取県伯耆町父原 伯耆 父原1号 12× VI 期-2
61 鳥取県伯耆町父原 伯耆 父原2号 9.5×6 VI 期-2 貼石なし
62 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原1号 6.5×5.4 V期-1
63 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原3号 4.2×3.9 V期-1
64 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原4号 4.3×3.6 V期-1
65 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原5号 2.1×2.0
66 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原7号 4.4×4.0 V期-1
67 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原8号 4.9×4.4 V期-1
68 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原9号 2.0×1.1 V期-1 墓上施設か
69 鳥取県大山町富岡 伯耆 洞ノ原10号 2.0×1.6 墓上施設か
70 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原11号 1.6×1.3 墓上施設か
71 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原12号 1.3×1.2 墓上施設か
72 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原13号 1.4×1.3 墓上施設か
73 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原16号 1.5× ?墓上施設か
74 鳥取県米子市淀江町 伯耆 洞ノ原17号 1.5×1.3 ?墓上施設か
75 鳥取県大山町富岡 伯耆 仙谷1号 13×13? V期-2
76 鳥取県大山町富岡 伯耆 仙谷2号 7.4×7.1 V期-2
77 鳥取県大山町長田 伯耆 徳楽 19×19 VI 期-2 未調査
鳥取県中部(倉吉市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
78 鳥取県倉吉市上神 伯耆 柴栗 V期-2 ?
79 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺1号 14× V期-2
80 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺2号 6× V期-2
81 鳥取県倉吉市下福田 伯耆 阿弥大寺3号 6× V期-2
82 鳥取県倉吉市山根 伯耆 藤和 10×8.5
83 鳥取県湯梨浜町宮内 伯耆 宮内1号 17× V期-2
鳥取県東部(鳥取市周辺)の四隅突出型型墳丘墓
84 鳥取県鳥取市桂見 因幡 西桂見 40以上× V期-3
85 鳥取県鳥取市国府町 因幡 糸谷1号 14×12 VI 期-2
兵庫県の四隅突出型型墳丘墓
86 兵庫県加西市網引町 播磨 周遍寺山1号 9.5×6 ??
87 兵庫県小野市船木町 播磨 船木南山 14× V期? ??
北陸・東北地方の四隅突出型型墳丘墓
88 福井県福井市清水町 越前 小羽山30号 26×22 V期-3 貼石なし
89 福井県福井市清水町 越前 小羽山33号 7×5 V期-3 ?貼石なし
90 福井県福井市高柳町 越前 高柳2号 6.2×5.5 VI 期-1 貼石なし
91 石川県白山市一塚町 加賀 一塚21号 18×18 VI 期-1 貼石なし
92 富山県富山市婦中町 越中 富崎1号 20×20 VI 期-2 貼石なし
93 富山県富山市婦中町 越中 富崎2号 20×20 VI 期-2 貼石なし
94 富山県富山市婦中町 越中 富崎3号 22×21 V期-3 貼石なし
95 富山県富山市婦中町 越中 六治古塚 24.5× VI 期-2 貼石なし
96 富山県富山市婦中町 越中 鏡坂1号 24.1× VI 期-1 貼石なし
97 富山県富山市婦中町 越中 鏡坂2号 13.7× VI 期-1 貼石なし
98 富山県富山市杉谷 越中 杉谷4号 25×25 VI期-2 貼石なし
99 富山県富山市古沢 越中 呉羽山丘陵No6 19×19 未調査
100 富山県富山市古沢 越中 呉羽山丘陵No10 23.5×22 未調査
101 富山県富山市金屋 越中 呉羽山丘陵No18 25×23 未調査
102 福島県喜多方市塩川町 石背 舘ノ内1号周溝墓 9×8 弥生末~古墳初 四隅突出型方形周溝墓
103 福島県喜多方市塩川町 石背 荒屋敷4号遺構 12× 弥生末~古墳初 四隅突出型方形周溝墓
資料 http://houki.yonago-kodaisi.com/zu-4sumi-1.jpg
■県別分布数
総数103基
島根県39基(邑南町1/ 隠岐の島西町1/ 出雲市11/ 松江市15/ 東出雲市1 /安来市10)
鳥取県28基(米子市11/ 伯耆町2/ 大山町7/ 倉吉市5/ 湯梨浜町1/ 鳥取市2)
福井県3基(福井市3)
石川県1基(白山市1)
富山県10基(富山市10)
広島県17基(三次市12/ 庄原市3/ 北広島町2)
岡山県1基(鏡野町1)
兵庫県2基(加西市1/小野市1)
福島県2基(喜多方市2)
相原精次・三橋浩『東北古墳探訪』彩流社より
総数103基
島根県39基(邑南町1/ 隠岐の島西町1/ 出雲市11/ 松江市15/ 東出雲市1 /安来市10)
鳥取県28基(米子市11/ 伯耆町2/ 大山町7/ 倉吉市5/ 湯梨浜町1/ 鳥取市2)
福井県3基(福井市3)
石川県1基(白山市1)
富山県10基(富山市10)
広島県17基(三次市12/ 庄原市3/ 北広島町2)
岡山県1基(鏡野町1)
兵庫県2基(加西市1/小野市1)
福島県2基(喜多方市2)
相原精次・三橋浩『東北古墳探訪』彩流社より
■築造年代と移動拡散
弥生中期後半から広島県の三次(みよし)盆地に発祥したという。 弥生後期後葉から美作・備後の北部地域や後期後半から出雲(島根県東部)・伯耆(鳥取県西部)を中心にした山陰地方に見られる墳丘墓である。北陸では少し遅れ能登半島などで造られている。源流は今のところ判明していないが、貼り石方形墓から発展したという可能性もある。
弥生中期後半から広島県の三次(みよし)盆地に発祥したという。 弥生後期後葉から美作・備後の北部地域や後期後半から出雲(島根県東部)・伯耆(鳥取県西部)を中心にした山陰地方に見られる墳丘墓である。北陸では少し遅れ能登半島などで造られている。源流は今のところ判明していないが、貼り石方形墓から発展したという可能性もある。
広島県三次市江の川中流域→美作・備後→島根半島西部→東部→伯耆→丹後→越前→会津
■編年図
まず近年、福島県の会津地方で二基確認され、大いに定説をおびやかしている。
また日本海沿岸でも、但馬、丹後、若狭にないこと、富山より東にないことが特徴である。若狭地域には同時期に方形貼石墓という様式の墓が流行しており、但馬出石では方形墓がある。つまり氏族の相違であろう。
これについてはすでに記事にしている。http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/56401410.html
方形貼石墓の分布は島根県地方などにも点々と及んでおり、例えば『播磨国風土記』のアメノヒボコとオオクニヌシの争いがこれに見合う記事となってはいる。ただし中心地である若狭湾西岸部の京都府にアメノヒボコの来訪があったかどうあかは定かでない。対岸にあたる東部ではツヌガアラシトの来訪が語られる。この二つの新羅王子の話が、同じ民族の渡来伝承であるならば、四隅突出型墳丘墓部族と方形貼石墓部族間の不和が起きて、鳥取などの戦争遺跡として残された可能性が出てくる。
また山口県土居ヶ浜遺跡の砂丘上墓もこれに関与した可能性も出てくるかもしれない。
また山口県土居ヶ浜遺跡の砂丘上墓もこれに関与した可能性も出てくるかもしれない。
この墳丘墓を作る氏族は最初、日本海沿岸ではなく中国山地中央部の三次盆地に定着している。突然山間部に彼らは姿を現しており、それ以前の経路が不明である。
朝鮮半島には、「朝鮮半島北部の滋江道蓮舞里で発見された墳墓に似ている。(上田正昭氏・古代出雲の研究課題)。基壇上に敷石の段差を二重に持つ(安養寺三号墳)ことから『高句麗将軍塚』に代表される高句麗積石塚に類似。(前島己基氏)が考えられ」るとする意見もあるがいまだ解明されていない。
朝鮮半島には、「朝鮮半島北部の滋江道蓮舞里で発見された墳墓に似ている。(上田正昭氏・古代出雲の研究課題)。基壇上に敷石の段差を二重に持つ(安養寺三号墳)ことから『高句麗将軍塚』に代表される高句麗積石塚に類似。(前島己基氏)が考えられ」るとする意見もあるがいまだ解明されていない。
●製鉄とともに広がるアカマツ林と古代の環境破壊
3000年前(弥生時代)寒冷化。稲作と金属器が入り、森林伐採と畑作開墾によって弥生人類による環境破壊が開始。近畿地方の植生はまだ激しい破壊にはなっていなかった=後進地帯だった。弥生の森林破壊は新しい植生を列島にもたらした。 顕著だったのはアカマツの林の拡大である。
つまり、アカマツと製鉄の増加は弥生時代の環境変化の大きな特徴であるから、それを持ち込んだのは明白に大陸の渡来技術者であることがわかるのだ。アカマツは風によって運ばれたこともあるが、これほど一気に環境を一変させたのは人為的なものが大きいということになるだろう。その人々は四隅突出型墳丘墓を作る人々だったでよかろう。すると想定できるのは高句麗人か百済人か伽耶か「新羅当時はまだシラ」か?
では高句麗地域ほかにアカマツや砂鉄や花崗岩や四隅突出型墳丘墓はあったかである。その人物像を特定したいなら墓の様式、製鉄、その素材が同じ場所を探すことである。わかったら探してください。そうすれば四隅突出型墳丘墓の被葬者たちがどこから来たかはあきらかになる。すると当時の中国・山陰・日本海の渡来勢力が見えてくる。筆者の推定では、現在、国情で発掘情況がまったくわからない北朝鮮国内にそれがあるような気がする。
四隅突出型墳丘墓は北朝鮮にある。と予言しておこう。
旧太田川河口部デルタ
※川を考えるときはいつも往古の形に焼きなおしてから考えねばならない。流れは時代ごとに変えられている。お忘れなく。太田川を知りたいなら、「旧太田川」で検索しましょう。タモリのようにね。