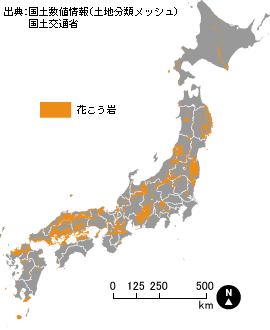『日本書紀』の最重要な記事である皇極天皇紀を読んでおいていただきたい。
ここには上宮王家の遭難。天変地異。秦河勝と東国多氏と常世の神、乙巳の変と大化の改新という、日本史上最重要の出来事が目いっぱい詰め込まれており、『日本書紀』とはまさにここを書くために存在するといってもよい肝の記事に仕上げてある。ここを読まずして『日本書紀』を読んだと言うなという重大な謎解き、ロジック解明のためのヒントがここにこそある。あえて全文掲載するのは、入鹿暗殺に至るまでの臨場感の盛り上がりをいかに作為してあるかを感じてもらいたいからである。
天皇紀から始まって、内容は次第に皇極を離れ、蘇我氏がいかに卑劣か、百済がそのときどのようになっていたか、誰を援助の相手として送り込んできたか、誰が逃げてきたか、百済王豊璋その他の重要な人物がどのように日本の王家へと変身したかが、ここには書かれてあるのだ。それはつまり天智=百済王子翹岐(ぎょうき)、鎌足=豊璋を歴然と暗示する内容になっているのだ!
『日本書紀』皇極天皇紀
●天皇出自紹介部分
天豊財重日【重日、此をば伊柯之比と云ふ】足姫天皇(皇極)は、渟中倉太珠敷天皇(敏達)の曾孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅渟王の女である。
母をば吉備姫王と曰す。天皇、古の道に順考へて、政をしたまふ。息長足日広額天皇(舒明)二年に、立ちて皇后と為りたまふ。十三年の十月に、息長足日広額天皇崩りましぬ。
●蝦夷・入鹿登場と百済の窮乏解説部分=いかに百済を助けねばならぬかの説得
元年の春正月の丁巳の朔辛未(642.01.15)に、皇后、即天皇位す。蘇我臣蝦夷を以て大臣とすること、故の如し。大臣の兒入鹿【更の名は鞍作】。自ら国の政を執りて、威父より勝れり。是に由りて、盜賊恐懾げて、路に遺拾らず。乙酉(01.29)に、百済の使人大仁阿曇連比羅夫、筑紫国より、駅馬に乗り来て言さく、
「百済国、天皇崩りましたりと聞りて、弔使を奉遣せり。臣、弔使に隨ひて、共に筑紫に到れり。而るに臣は葬に仕らむことを望ふ。故、先ちて独り来り。然も其の国は、今大きに乱れたり」
とまうす。
二月の丁亥の朔戊子(02.02)に、阿曇山背連比羅夫・草壁吉士磐金・倭漢書直縣をして、百済の弔使の所に遣して、彼の消息を問はしむ。弔使報して言さく、
「百済国の主、臣に謂りて言ひしく、『塞上恒に作悪す。還使に付けたまはむと請すとも、天朝許したまはず』といひき」
とまうす。
百済の弔使の人等言く、「去年十一月、大佐平智積卒せぬ。又百済の使人、崐崘の使を海裏に擲れたり。今年の正月に、国の主の母薨せぬ。又弟王子、兒翹岐及び其の母妹の女子四人、内佐平岐味、高き名有る人四十余、嶋に放たれぬ」といふ。
壬辰(02.06)に、高麗の使人、難波津に泊れり。丁未(02.21)に、諸の大夫を難波郡に遣して、高麗国の貢れる金銀等、幷て其の獻る物を検へしむ。使人、貢獻ること既に訖りて、諮して云さく、
「去年の六月に、弟王子薨せぬ。秋九月に、大臣伊梨柯須弥、大王を弑し、幷て伊梨渠世斯等百八十余人を殺せり。仍りて弟王子の兒を以て王とせり。己が同姓都須流金流を以て大臣とす」
とまうす。
●高句麗も救援必要の解説部分=いかに新羅が悪辣で滅ぼすべき相手か
戊申(02.24)に、高麗・百済の客に難波郡に饗へたまふ。大臣に詔して曰はく、
「津守連大海を以て高麗に使すべし。国勝吉士水鶏を以て百済に使はすべし。【水鶏、此をば倶毗那と云ふ】。草壁吉士眞跡を以て新羅に使はすべし。坂本吉士長兄を以て任那に使すべし」
とのたまふ。
庚戌(02.24)に、翹岐を召して、阿曇山背連の家に安置らしむ。辛亥(02.25)に、高麗・百済の客に饗へたまふ。癸丑(02.27)に、高麗の使人・百済の使人、並に罷り帰る。
●天候記事の連続=滅びてしかるべしの予兆を臨場感しだいに盛り上げる演出
三月の丙辰の朔戊午(03.03)に、雲無くして雨ふる。辛酉(03.06)に、新羅、賀騰極使と喪を弔ふ使とを遣す。庚午(03.15)に、新羅の使人罷り帰る。是の月に、霖雨す。
●百済王子翹岐、救援要請大使として来日=延々と翹岐の名前を出しては百済の重要性を説く
夏四月の丙戌の朔癸巳(04.08)に、大使翹岐、其の従者を將て朝に拜す。乙未(04.08)に、蘇我大臣、畝傍の家にして、百済の翹岐等を喚ぶ。親ら對ひて語話す。仍りて良馬一匹・鐵廿铤を賜ふ。唯し塞上をのみ喚ばず。是の月に、霖雨す。
五月の乙卯の朔己未(05.05)に、河内国の依網屯倉の前にして、翹岐等を召びて、射猟を観しむ。庚午(05.16)に、百済国の調の使の船と吉士の船と、倶に難波津に泊れり。【蓋し吉士は前に使を百済に奉りたるか】。壬申(05.18)に、百済の使人調進る。吉士服命す。乙亥(05.21)に、翹岐が從者一人死去ぬ。丙子(05.22)に、翹岐が兒死去ぬ。(家族ぐるみで来日しており翹岐はつまり逃避行だったのだ)
是の時に、翹岐と妻と、兒の死にたることを畏ぢ忌みて、果して喪に臨ず。凡そ百済・新羅の風俗、死亡者有るときは、父母兄弟夫婦姉妹と雖も、永ら自ら看ず。此を以て観れば、慈、無きが甚しきこと、豈に禽獸に別ならむや。丁丑(05.23)に、熟稻始めて見ゆ。戊寅(05.24)に、翹岐、其の妻子を將て、百済の大井の家に移る。乃ち人を遣りて兒を石川に葬る。
六月の乙酉の朔庚子(06.16)に、微雨ふる。是の月に、大きに旱る
秋七月の甲寅の朔壬戌(07.09)に、客星月に入れり。乙亥(07.22)に、百済の使人大佐平智積等に朝に饗へたまふ。
【或本に云く、百済使人大佐平智積及び兒達率 、名を闕せり・恩率軍善といふ】。
●翹岐の弟子・智積登場、瑞兆である白い雀記事
乃ち健兒に命せて、翹岐が前に相撲らしむ。智積等、宴畢りて退でて、翹岐が門を拜す。丙子(07.23)に、蘇我臣人鹿が豎者、白雀の子を獲る。
●古い悪癖である牛馬の生贄や河伯信仰を蘇我氏が強引に仏教にかえさせた
是の日の同じ時に、人有りて、白雀を以て籠に納れて、蘇我の大臣に送る。戊寅(07.25)に、群臣相ひ謂りて曰く、「村々の祝部の所教の隨に、或いは牛馬を殺して、諸の社の神を祭る。或いは頻に市を移す。或いは河伯を禱る。既に所效無し」といふ。蘇我大臣報へて曰く、
「寺々にして大乗経典を転読みまつるべし。悔過すること、仏の説きたまふ所の如くして、敬びて雨を祈はむ」
といふ。
●蝦夷の雨乞い=シャーマン王であるのに外国の仏教を流布しようとしている
庚辰(07.28)に、大寺の南の庭にして、仏、菩薩の像と四天王の像とを厳ひて、衆の僧を屈び請せて、大雲経等を読ましむ。時に、蘇我大臣、手に香鑪を執りて、香を燒きて願を発す。辛巳(07.28)に、微雨ふる。壬午(07.29)に、雨を祈ふこと能はず。故、経を読むことを停む
八月の甲申の朔(08.01)に、天皇、南淵の河上に幸して、跪きて四方を拜む。天を仰ぎて祈ひたまふ。即ち雷なりて大雨ふる。遂に雨ふること五日。溥く天下を潤す
【或本に云く、五日連に雨ふりて、九穀登り熟めりといふ】
是に、天下の百姓、倶に称万歳びて曰さく、「至徳まします天皇なり」とまうす。
●百済の使者また来る、高句麗と新羅の使者はばかって帰国=百済重視
己丑(08.06)に、百済の使参官等罷り帰る。仍りて大舶と同船と三艘を賜ふ【同船は、母慮紀舟といふ】。是の日の夜半に、雷、西南の角に鳴りて、風ふき雨ふる。參官等が乗る所の船舶、岸に触きて破れぬ。丙申(08.13)に、小を以て百済の質達率長福を授けたまふ。中客より以下に、位一級を授けたまふ。物を賜ふこと各差有り。戊戌(08.15)に、船を以て百済の參官等に賜ひて、発て遣す。己亥(08.16)に、高麗の使人、罷り帰る。己酉(08.26)に、百済・新羅の使人、罷り帰る。
●皇極、百済大寺の建立を発願=蘇我にそそのかされ牛耳られた女帝
九月の癸丑の朔乙卯(09.03)に、天皇、大臣に詔して曰はく、「朕、大寺を起し造らむと思欲ふ。近江と越の丁を発せ」とのたまふある【百済大寺ぞ】。
復、諸国に課せて、船舶を造らしむ。辛未(09.19)に、天皇、大臣に詔して曰はく、「是の月に起して十二月より以來を限りて、宮室を営らむと欲ふ。国国に殿屋材を取らしむべし。然も東は遠江を限り、西は安芸を限りて、宮を造る丁を発せ」とのたまふ。癸酉(09.21)に、越の辺の蝦夷、数千内附く。
●天変地異=革命・クーデターの予感
冬十月の癸未の朔庚寅(10.08)に、地震り雨ふる。辛卯(10.09)に、地震る。是の夜、地震り風ふく。甲午(10.12)に、蝦夷に朝に饗たまふ。丁酉(10.15)に、蘇我大臣、蝦夷に家に設して、躬ら慰め問ふ。是の日に、新羅の弔使の船と賀騰極使の船、壹岐嶋に泊れり。丙午(10.24)の夜中に、地震る。
是の月に、夏の令を行ふ。雲無くして雨ふる。
十一月の壬子の朔癸丑(11.02)に、大雨ふり雷なる。丙辰(11.05)の夜半、雷一西北の角に鳴る。己未(11.08)に、雷五西北の角に鳴る。庚申(11.09)に、天の暖なること春の気の如し。辛酉(11.10)に、雨下る。壬戌(11.11)に、天の暖なること春の気の如し。甲子(11.11)に、雷一北の方に鳴りて、風発る。丁卯(11.16)に、天皇新嘗御す。是の曰に、皇子・大臣、各自ら新嘗す。
●舒明陵墓の改葬
十二月の壬午の朔(12.01)に、天の暖なること春の気の如し。甲申(12.03)に、雷、五昼鳴り、二夜に鳴る。甲午(12.13)に、初めての喪を発す。是の日に、小徳巨勢臣徳太、大派皇子に代りて誄す。次に小徳粟田臣細目、軽皇子に代りて誄す。次に小徳大伴連馬飼、大臣に代りて誄す。乙未(12.14)に、息長山田公、日嗣を誄び奉る。辛丑(12.20)に、雷三東北の角に鳴る。庚寅(12.09)に、雷二東に鳴りて、風ふき雨ふる。壬寅(12.21)に、息長足日廣額天皇を滑谷岡に葬りまつる。是に日に、天皇、小墾田宮に遷移りたまふ
【或本に云はく、東宮の南の庭の権宮に遷りたまふといふ】。
●蝦夷、八佾の舞=大王の振る舞い
甲辰(12.23)に、雷一夜に鳴る。其の声裂くるが若し。辛亥(12.30)に、天の暖なること春の気の如し。
是歳、蘇我大臣蝦夷、己が祖廟を葛城の高宮に立てて、八佾の儛をす。遂に歌を作りて曰く、
野麻騰能、飫斯能毗稜栖鳴、倭柁羅務騰、阿庸比陀豆矩梨、舉始豆矩羅符母。
大和(やまと)の 忍(おし)の広瀬(ひろせ)を 渡(わた)らむと 足結(あよひ)手作(たづく)り 腰作(こしづく)らふも
●蘇我大墓・小墓の造営=天皇を上回る巨大さだ
又尽に国挙る民、幷て百八十部曲を発して、預め双墓を今来に造る。一つをば大陵と曰ふ。大臣の墓とす。一つをば小陵と曰ふ。入鹿臣の墓とす。望はくは死りて後に、人を労らしむること勿。更に悉に上宮の乳部の民を聚めて、
【乳部、此をば美父と云ふ】
塋垗所に役使ふ。是に、上宮大娘姫王、発憤りて歎きて曰く、
「蘇我臣、専国の政を擅にして、多に行無礼す。天に二つの日無く、国に二の王無し。何に由りてか意の任に悉に封せる民を役ふ」
といふ。茲より恨を結びて、遂に倶に亡されぬ。是年、太歳壬寅。
●五色の雲=時は来た!
二年の春正月の壬子の朔の旦(643.01.02)に、五つの色の大きなる雲、天に満み覆ひ、寅に闕けたり。一つの色の青き霧、周に地に起る。辛酉に、大風ふく。
二月の辛巳の朔の庚子(02.20)に、桃の花始めて見ゆ。乙巳(02.25)に、雹ふりて草木の花葉を傷せり。
是の月に、風ふき雷なり雨氷ふる。冬の令を行へばなり。国の内の巫覡等、枝葉を折り取りて、木綿を縣掛けて、大臣の橋を渡る時を伺候ひて、爭ぎて語の入微なる説を陳ぶ。其の巫甚多にして、悉に聴くべからず。
三月の辛亥の朔癸亥(03.13)に、難波の百済の客の館堂と、民の家屋とに災けり。乙亥(03.25)に、霜ふりて草木の花葉を傷せり。
是の月に、風ふき雷なりて雨氷ふる。冬の令を行へばなり。
夏四月の庚辰の朔丙戌(04.07)に、大きに風ふきて雨ふる。丁亥(04.06)に、風起りて天寒し。己亥(04.20)に、西の風ふきて雹ふれり。天寒し。人綿袍三領を着る。庚子(04.21)に、筑紫大宰、馳驛して奏して曰さく、「百済国の主の兒、翹岐・弟王子、調の使と共に来たり」とまうす。丁未(04.28)に、権宮より移りて飛鳥の板蓋の新宮に幸す。甲辰(04.25)に、近江国言さく、「雹下れり。其の大きさの経一寸」とまうす。
●月食=いよいよ蘇我王家の命運はつきたぞ!
五月の庚戌の朔乙丑(05.16)に、月蝕えたること有り。
六月の己卯の朔辛卯(06.13)に、筑紫大宰、馳駅して奏して曰さく、[高麗、使を遣して来朝さしむ」とまうす。群卿聞きて、相謂りて曰く、「高麗、己亥の年より朝らず。而るを今年朝り」といふ。辛丑(06.23)に、百済の調進る船、難波の津に泊れり。
秋七月の己酉の朔辛亥(07.03)に、數大夫を難波郡に遣はして、百済国の調と献れる物とを検へしむ。是に、大夫、調の使に問ひて曰く、「進れる国の調、前の例より欠少、大臣に送れる物、去年還せる色を改めず、群卿に送れる物、亦全ら将来らず、皆前の例に違へり。其の状は何ぞ」といふ。大使達率自斯・副使恩率軍善、倶に答へ諮して曰さく、「即今に備ふべし」とまうす。自斯は、質達率武子が子なり。
是の月に、茨田池の水大きに臭りて、小き虫水に覆へり。其の虫、口は黒くして身は白し
●茨田池あふれる
八月の戊申の朔壬戌(08.15)に、茨田池の水、変りて藍の汁の如し。死にたる虫水に覆へり。溝瀆の流、亦復凝結れり。厚さ三四寸ばかり。大きに小き魚の臭れること、夏に爛れ死にたるが如し。是に由りて、喫に中らず。
九月の丁丑の朔壬午(09.06)に、息長足日廣額天皇を押坂陵に葬りまつる【或本に云はく、広額天皇を呼して、高市天皇とすといふ】。丁亥(09.11)に、吉備嶋皇祖母命薨りましぬ。癸巳(09.17)に、土師娑婆連猪手に詔して、皇祖母命の喪を視しむ。天皇、皇祖母命の臥病したまひしより、喪を発すに至る及に、床の側を避りたまはずして、視養たてまつりたまふこと倦ること無し。乙未(09.19)に、皇祖母命を檀弓岡に葬りまつる。是の日に、大雨ふりて雹ふる。丙午(09.30)に、皇祖母命の墓造る役を罷めしむ。仍、臣、連、伴造に帛布を賜ふこと、各差有り。
是の月に、茨田池の水、漸々に変りて白き色に成りぬ。亦臭き気無し。
●勝手に紫金の冠を入鹿にかぶせやがった!勝手に自分の子である古人大兄を皇太子にした!蝦夷の妻は大罪人物部守屋の妹だぞ!上宮王家をないがしいろにしたぞ!
冬十月の丁未の朔己酉(10.03)に、群臣、伴造に朝堂の庭に饗たまひ賜ふ。而して位を授けたまふ事を議る。遂に国司に詔したまはく、「前の勅せる所の如く、更改め換ること無し。厥の任けたまへるところに之りて、爾の治す所を愼め」とのたまふ。壬子(10.06)に、蘇我大臣蝦夷、病に縁りて朝らず。私に紫冠を子入鹿に授けて、大臣の位に擬ふ。復其の弟を呼びて、物部大臣と曰ふ。大臣の祖母は、物部弓削大連の妹。故母が財に因りて、威を世に取れり。戊午(10.12)に、蘇我臣入鹿、独り謀りて、上宮の王等を廃てて、古人大兄を立てて天皇とせむとす。時に、童謠有りて曰く、
伊波能杯儞 古佐屢渠梅野倶 渠梅多儞母 多礙底騰裒羅栖 歌麻之々能烏膩
岩(いは)の上(へ)に 小猿(こさる)米(こめ)焼(や)く 米(こめ)だにも 食(た)げて通(とほ)らせ 山羊(かましし)の老翁(をぢ)
【蘇我臣入鹿、深く上宮の王等の威名ありて、天下に振すことを忌みて、独り僭ひ立たむことを謨る】。是の月に、茨田池の水、還りて清みぬ。
●上宮王家遭難滅亡
十一月の丙子の朔(11.01)に、蘇我臣入鹿、小徳巨勢徳太臣・大仁土師娑婆連を遣りて、山背大兄王等を斑鳩に掩(おそ)はしむ。【或本に云はく、巨勢徳太臣・倭馬飼首を以て将軍とすといふ】。是に、奴三成、数十の舍人と、出でて拒き戦ふ。土師娑婆連、箭に中りて死ぬ。軍の衆恐り退く。軍の中の人、相謂りて曰く、「一人当千といふは、三成を謂ふか」といふ。山背大兄、仍りて馬の骨を取りて、内寢に投げ置く。遂に其の妃、幷びに子弟等を率て、間を得て逃げ出でて、膽駒山に隠れたまふ。三輪文屋君・舍人田目連及び其の女・菟田諸石・伊勢阿部堅経、従(みとも)につかへまつる。巨勢徳太臣等、斑鳩宮を焼く。灰の中に骨を見でて、誤りて王死せましたりと謂ひて、囲を解きて退き去る。是に由りて、山背大兄王等、四五日の間、山に淹留(とどま)りたまひて、得喫飲(ものもえまうのぼ)らず。三輪文屋君、進みて勧めまつりて曰さく、「請ふ、深草屯倉に移向(ゆ)きて、兹より馬に乗りて、東国に詣りて、乳部を以て本として、師を興して還りて戦はむ。其の勝たむこと必じ」といふ。山背大兄王等対へて曰はく、「卿が噵ふ所の如くならば、其の勝たむこと必ず然らむ。但し吾が情に冀(ねがはく)は、十年百姓を役(つか)はじ。一の身の故を以て、豈万民を煩労はしめむや。又後世に、民の吾が故に由りて、己が父母を喪せりと言はむことを欲(ほ)りせじ。豈其れ戦ひ勝ちて後に、方に丈夫と言はむや。夫れ身を損てて国を固めば、亦丈夫にあらずや」とのたまふ。
人有りて遙に上宮の王等を山中に見る。還りて蘇我臣入鹿に噵ふ。入鹿、聞きて大きに懼ず。速に軍旅を発して、王の在します所を高向臣国押に述りて曰く、「速に山に向きて彼の王を求(かす)べ捉(から)むべし」といふ。国押、報へて曰く、「僕は天皇の宮を守りて、敢へて外に出でじ」といふ。入鹿即ち自ら往かむとす。
時に、古人大兄皇子、喘息(いわ)けて来して問ひたまはく、「何処か向く」とのたまふ。入鹿、具に所由を説く。古人皇子の曰はく、「鼠は穴に伏れて生き、穴を失ひて死ぬと」とのたまふ。入鹿是に由りて行くことを止む。
軍将等を遣りて、膽駒に求めしむ。竟(つひ)に覓(もとめう)ること能はず。是に、山背大兄王等、山より還りて、斑鳩寺に入ります。軍将等即ち兵を以て寺を囲む。是に、山背大兄王、三輪文屋君をして軍将等に謂らはしめて曰はく、「吾、兵を起して入鹿を伐たば、其の勝たむこと定(うつむな)し。然るに一つの身の之故に由りて、百姓を残(やぶ)り害はむことを欲(ほ)りせじ。是を以て、吾が一つの身をば、入鹿に賜ふ」とのたまひ、終に子弟、妃妾と一時に自ら経(わな)きて倶に死せましぬ。時に、五つの色の幡蓋、種々の伎樂、空に照灼りて、寺に臨み垂れり。衆人仰ぎ観、称嘆きて、遂に入鹿に指し示す。其の幡蓋等、変りて黒き雲に為りぬ。是に由りて、入鹿見ること得るに能はず。蘇我大臣蝦夷、山背大兄王等、総て入鹿に亡さるといふことを聞きて、嗔り罵りて曰く、「噫、入鹿、極甚だ愚癡にして、専行暴悪す。儞が身命、亦殆からずや」といふ。時の人、前の謠の応を説きて曰く、「『岩(いは)の上(うへ)に』といふを以ては、上宮に喩ふ。『小猿(こさる)』といふを以ては、林臣に喩ふ【林臣、入鹿ぞ】。『米焼(こめや)く』といふを以ては、燒上宮を焼くに喩ふ。『米(こめ)だにも 食(た)げて通(とほ)らせ 山羊(かましし)の老翁(をぢ)』といふを以ては、山背王の頭髮斑雜毛にして山羊に似るに喩ふ。又其の宮を棄捨てて深き山に匿れし相なり。
是歳、百済の太子余豊、蜜蜂の房四枚を以て、三輪山に放ち養ふ。而して終に蕃息らず。
●鎌足突然の登場
三年の春正月の乙亥の朔(644.01.01)に、中臣鎌子連を以て神祗伯に拝(め)す。再三に固辞(いな)びて就(つかへまつ)らず。疾を称して退でて三嶋に居り。時に、軽皇子、患脚(みあしのやまひ)して朝(まゐりつか)へず。中臣鎌子連、曾(いむさき、すでに、以前)より軽皇子に善(うるは)し。故彼の宮に詣でて、侍宿(とのゐにはべ)らむとす。軽皇子、深く中臣鎌子連の意気高く逸(すぐ)れて容止(かたち)犯(な)れ難きことを識りて、乃ち寵妃阿倍氏を使ひたまひて、別殿を淨め掃へて、新しき蓐を高く鋪(し)きて、具(とも)に給(つ)がずといふこと靡(な)からしめたまふ。敬び重(あが)めたまふこと特(こと)に異(け)なり。中臣鎌子連、便ち遇(めぐ)まるるに感(かま)けて、舍人に語りて曰く、「殊に恩沢(みうつくしび)を奉ること、前より望(ねが)ひし所に過ぎたり。誰か能く天下に王(きみ)とましまさしめざらむや」といふ。【舍人を充てて駈使(つかひ)とせるを謂ふ】。舍人、便ち語らふ所を以て、皇子に陳(まう)す。皇子大きにびたまふ。中臣鎌子連、人と爲りて忠正しくして、匡し済(すく)ふ心有り。乃ち、蘇我臣入鹿が、君臣長幼の序を失ひ、社稷を𨶳(門視)𨵦(門兪)(うかがふ)ふ権(はかりごと)を挾(わきばさ)むことを憤(いく)み、歷試(つた)ひて王宗のに中に接(まじは)りて、功名(いたはり)を立つべき哲主(さかしききみ)をば求む。便ち心を中大兄に附くれども、䟽然(さかり)て未だ其の幽抱(ふかきおもひ)を展ぶること獲ず。
●中大兄突然登場と鎌足の蹴鞠密談
偶(たまたま)中大兄の法興寺の槻の樹の下に打毱(まりく)うる侶に預りて、皮鞋の毱の隨(まま)脱け落つるを候(まも)りて、掌中に取り置ちて、前みて跪きて恭みて奉る。中大兄、対(むか)ひ跪きて敬びて執りたまふ。兹より、相(むつ)び善(よ)みして、倶に懷ふ所を述ぶ。既に匿るる所無し。後に他の頻に接はることを嫌はむをことを恐りて、倶に手に黄卷(ふみまき)を把りて、自ら周孔の教を南淵先生の所に学ぶ。遂に路上、往還ふ間に、肩を並べて潜に図る。相ひ協はずといふこと無し。是に、中臣鎌子連議りて曰さく、「大きなる事を謀るには、輔(たすけ)有るに如かず。
●蘇我倉山田一族の仲介
請ふ、蘇我倉山田麻呂の長女を納れて妃として、婚姻の眤(むつみ)を成さむ。然して後に陳べ説きて、与に事を計らむと欲ふ。功を成す路、兹より近きは莫し」とまうす。中大兄、聞きて大きにびたまふ。曲に議る所に従ひたまふ。中臣鎌子連、即ち自ら往きて媒(なかだ)ち要(かた)め訖りぬ。而るに長女、期(ちぎ)りし夜、族に偸(ぬす)まれぬ。【族は身狹臣を謂ふ】。是に由りて、倉山田臣、憂へ惶(かしこま)り、仰ぎ臥して所爲知らず。少女、父の憂ふる色を怪びて、就きて問ひて曰く、「憂へ悔ゆること何ぞ」といふ。父其の由を陳ぶ。少女曰く、「願はくはな憂へたまひそ。我を以て奉進りたまふとも、亦復晩(おそ)からじ」といふ。父、便ち大きにびて、遂に其の女を進る。奉るに赤心を以てして、更に忌む所無し。中臣鎌子連、佐伯連子麻呂・葛城稚犬養連網田を中大兄に挙げて曰く、云々。
●アンチ瑞兆=ふくろう=ずるがしこさの象徴
三月に、休留、【休留は茅鴟なり】。豊浦大臣の大津の宅の倉に子を産めり。倭国言さく、「頃者、菟田郡の人押坂直【名を闕せり】。一の童子を将て、雪の上に欣遊(うれ)しぶ。菟田山に登りて、便ち紫の菌の雪より挺て生ふるを看る。高さ六寸余。四町許に満めり。乃ち童子をして採取りて、還りて隣の家に示す。総言はく、『知らず』といふ。且毒しき物なりと疑ふ。是に、押坂直と童子と、煮て食ふ。大だ気しき味有り。明日往きて見るに、都て不在し。押坂直と童子と、菌の羹を喫へるに由りて、病無くして寿し」とまうす。或人の云く、「蓋し、俗、芝草といふことを知らずして、妄に菌と言へるか」といふ。
●奇談
夏六月の癸卯の朔(06.01)に、大伴馬飼連、百合の花を献れり。茎の長さ八尺。其の本異にして末連(あ)へり。乙巳(06.03)に、志紀上郡言さく、「人有りて、三輪山にして、猿の昼睡るを見て、窃かに其の臂を執へて、其の身を害らず。猿猶合眼(ねぶ)りて歌して曰く、
武舸都烏爾 陀底屢制囉我 儞古泥舉曾 倭我底烏騰羅毎、拕我佐基泥 佐基泥曾母野 倭我底騰羅須謀野
向(むか)つ嶺(を)に 立(たて)てる夫(せ)らが 柔手(にこで)こそ 我(わ)が手(て)を取(と)らめ 誰(た)が裂手(さきで) 裂手(さきで)そもや 我(わ)が手(て)取(とら)らすもや
其の人、猿の歌を驚き怪びて、放捨(す)てて去りぬ。此は是、数年を経歴(へ)て、上宮の王等の、蘇我鞍作が爲に、胆駒山に囲るる兆なり。戊申(06.06)に、剣池の蓮の中に、一つの茎に二つの萼ある者有り。豊浦大臣、妄りに推して曰く、「是れ、蘇我臣の栄えむとする瑞なり」といふ。即ち金の墨を以て書きて、大法興寺の丈六の仏に献る。
●蝦夷の傍若無人
是の月に、国の内の巫覡等、枝葉を折り取りて、木綿に懸掛(しでか)けて、大臣の橋を渡る時を伺ひて、争(いそ)ぎて神語の入微(たへ)なる説(ことば)を陳ぶ。其の巫甚多(にへさ)なり。具に聴くべからず。老人等の曰、「移風らむ兆なり」といふ。時に、謠歌三首有り。其の一に曰く、
波魯波魯儞 渠騰曾枳舉喩屢、之麻能野父播羅。
遥遥(ほろほろ)に 言(こと)そ聞(きこ)ゆる 嶋(しま)の藪原(やぶはら)
其の二に曰く、
烏智可拕能、阿娑努能枳々始、騰余謀作儒、倭例播禰始柯騰、比騰曾騰余謀須。
彼方(をちかた)の 浅野(あさの)の雉(きぎし) 響(とよも)さず 我(われ)は寝(ね)しかど 人(ひと)そ響(とよも)す
其三曰、
烏麼野始儞、倭例烏比岐例底、制始比騰能、於謀提母始羅孺、伊弊母始羅孺母。
小林(をばやし)に 我(われ)を引(ひ)きいれ 姧(せ)し人(ひと)の 面(おもて)も知(し)らず 家(いへ)も知(も)らず
向うの嶺にいる男等の やさしい手ならば 私の手をとってほしいものを 誰かの荒々しい手で 荒々しい手ですってよくもまあ 私の手をどうしてとらせてあげられましょう。
●東国多氏の勝手な信仰、河勝これを打つ、古い常世信仰の押し込め
秋七月に、東国の不尽河の辺の人大生部多、虫祭ることを村里の人に勧めて曰く、「此は常世の神なり。此の神を祭る者は、富と寿とを致す」といふ。巫覡等遂に詐きて、神語に託せて曰く、「常世神を祭らば、貧しき人は富を致し、老いたる人は還りて少(わか)ゆ、是に由りて、加(ますます)勧め、民の家の財宝を捨てしめ、酒を陳ね、菜、六畜を路の側に陳ねて、呼ばはしめて曰く、「新しき富入来れり」といふ。都鄙の人、常世の虫を取りて、清座に置きて、歌ひ儛ひて、福を求めて珍財を棄捨つ。都(かつ)て益す所無くして、損(おと)り費ゆること極めて甚し。是に、葛野の秦造河勝、民の惑はさるを悪みて、大生部多を打つ。其の巫覡等、恐りて勧め祭ることを休む。時の人便ち歌を作りて曰く、
禹都麻佐波 柯微騰母柯微騰 枳舉曳倶屢 騰舉預能柯微乎 宇智岐多麻須母
太秦(うつまさ)は 神(かみ)とも神(かみ)と 聞(きこ)え来(く)る 常世(とこよ)の神(かみ)を 打(う)ち懲(きた)ますも
此の虫は、常に於橘の樹に生る。或いは曼椒に生る【曼椒、此をば褒曾紀と云ふ】。其の長さ四寸余、其の大きさ頭指許。其の色緑にして有黒点(くろまだら)なり。其の㒵(かたち)全ら養蚕に似れり。
●蘇我氏豪邸
冬十一月に、蘇我大臣蝦夷・兒入鹿臣、家を甘檮岡に双べ起つ。大臣の家を呼びて、上の宮門と曰ふ。入鹿が家をば、谷の宮門【谷、此をば波佐麻と云ふ】と曰ふ。。男女を呼びて王子と曰ふ。家の外に城柵を作り、門の傍に兵庫を作る。門毎に、水盛るる舟一つ、木鉤数十を置きて、火の災に備ふ。恆に力人をして兵を持ちて家を守らしむ。大臣、長直をして、大丹穗山に、桙削寺を造らしむ。更家を畝傍山の東に起つ。池を穿りて城とせり。庫を起てて箭を儲(つ)む。恒に五十の兵士を将て、身に繞(めぐ)らして出入す。健人を名づけて東方の儐從者と曰ふ。氏々の人等、入りて其の門に侍り。名づけて祖子孺者と曰ふ。漢直等、全ら二つの門に侍り。
四年の春正月(645.01.01)に、或いは阜嶺に、或いは河辺に、或いは宮寺の間にして、遙に見るに物有り。而して猴の吟を聴く。或いは一十許、或いは二十許。就きて視れば、物便ち見へずして、尚鳴き嘯く響聞ゆ。其の身を覩ること獲るに能はず。
【旧本に云く、是歳、京を難波に移す。而して板蓋宮の墟と爲らむ兆なりといふ】。時の人の曰く、「此は是、伊勢大の使なり」といふ。
●高句麗僧鞍作を謀殺=入鹿の死をにおわす
夏四月の戊戌の朔(04.01)に、高麗の学問僧等言さく、「同学鞍作得志、虎を以て友として、其の術を学び取れり。或いは枯山をして変へて青山にす。或いは黄なる地をして変へて白き水にす。種々の奇しき術、殫して究むべからず。又、虎、其の針を授けて曰く、「愼矣愼矣、人をして知らしむること勿れ。此を以て治めれば、病愈えずといふこと無し」といふ。果して言ふ所の如くに、治さめて差えずといふこと無し。得志、恒に其の針を以て柱の中に隠し置けり。後に、虎、其の柱を折りて、針を取りて走去げぬ。高麗国、得志が帰らむと欲ふ意を知りて、毒を与へて殺す。
●乙巳の変
六月の丁酉の朔甲辰(06.08)に、中大兄、密に倉山田麻呂臣に謂りて曰く、「三韓の調を進らむ日に、必ず将に卿をして其の表を読み唱げしめむ」といふ。遂に入鹿を斬らむとする謀を陳ぶ。麻呂臣許し奉る。戊申(06.12)に、天皇大極殿に御(おはしま)す。古人大兄侍り。中臣鎌子連、蘇我入鹿臣の、人と爲り疑多くして、昼夜剣持けることを知りて、俳優に教へて、方便(たばか)りて解(ぬ)かしむ。入鹿臣、咲ひて剣を解く。入りて座に侍り。倉山田麻呂臣、進みて三韓の表文を読み唱(あ)ぐ。是に、中大兄、衞門府に戒めて、一時に倶に十二の通門を鏁めて、往来はしめず。衞門府を一所に召し聚めて、将に給禄(ものさづ)けむとす。時に、中大兄、即ち自ら長き槍を執りて、殿の側に隠れたり。中臣鎌子連等、弓矢を持ちて爲助衞(ゐまも)る。海犬養連勝麻呂をして、箱の中の両つの剣を佐伯連子麻呂と葛城稚犬養連網田とに授けしめて曰く、「努力努力、急須(あからさま)に斬るべし」といふ。子麻呂等、水を以て送飯(いひす)く。恐りて反吐(たまひいだ)す。中臣鎌子連、嘖めて励ましむ。倉山田麻呂臣、表文を唱ぐること将に尽きなむとすれども、子麻呂等の来ざることを恐りて、流づる汗身に浹(あまね)くして、声乱れて動(わなな)く。鞍作臣、怪びて問ひて曰く、「何故か掉(ふる)ひ戦(わなな)く」といふ。山田麻呂対へて曰く、「天皇に近つける恐(かしこ)みに、不覺にして汗流づる」といふ。
中大兄、子麻呂等の、入鹿が威に畏りて、便旋ひて進まざるを見て曰はく、「咄嗟」とのたまふ。即ち子麻呂等と共に、出其不意(ゆくりもな)く、剣を以て入鹿が頭肩を傷り割ふ。入鹿驚きて起つ。子麻呂、手を運し剣を揮きて、其の一つの脚を傷りつ。入鹿、御座に転び就きて、叩頭みて曰さく、「当に嗣位に居すべきは、天子なり。臣罪を知らず。乞ふ、垂審察(あきらめたま)へ」とまうす。天皇大きに驚きて、中大兄に詔して曰はく、「知らず、作る所、何事有りつるや」とのたまふ。中大兄、地に伏して奏して曰さく、「鞍作、天宗を尽くし滅して、日位を傾けむとす。豈天孫を以て鞍作に代へむや」とまうす。【蘇我臣入鹿、更の名は鞍作】。天皇、即ち起ちて殿の中に入りたまふ。佐伯連子麻呂・稚犬養連網田、入鹿臣を斬りつ。是の日に、雨下りて潦水庭に溢めり。席障子を以て、鞍作が屍に覆ふ。古人大兄、見て私の宮に走り入りて、人に謂ひて曰く、「韓人、鞍作臣を殺しつ。【韓政に因りて誅せらるるを謂ふ】 吾が心痛し」といふ。即ち臥内に入りて、門を杜して出でず。中大兄、即ち法興寺に入りて、城として備ふ。凡て諸の皇子、諸王、諸卿大夫、臣、連、伴造、国造、悉に皆隨侍り。人をして鞍作臣の屍を大臣蝦夷に賜はしむ。是に、漢直等、眷属を総べ聚め、甲を擐、兵を持ちて、大臣を助けて軍陣を処き設けむとす。中大兄、将軍巨勢陀臣を使して、天地開闢けてより、君臣始めて有つことを以て、賊の党に説かしめたまひて、赴く所を知らしめたまふ。是に、高向臣国押、漢直等に謂りて曰く、「吾等、君大郎に由りて、戮されぬべし。大臣も、今日明日に、立(たちどころ)に其の誅されむことを俟たむこと決(うつむな)し。然らば誰が爲に空しく戦ひて、尽に刑せられむか」と言ひ畢りて、剣を解き弓を投りて、此を捨てて去る。賊の徒亦隨ひて散り走ぐ。
己酉(06.13)に、蘇我臣蝦夷等、誅されむとして、悉に天皇記・国記・珍宝を焼く。船史惠尺、即ち疾く、焼かるる国記を取りて、中大兄に奉献る。是の日に、蘇我臣蝦夷及び鞍作が屍を、墓に葬ることを許す。復哭泣を許す。是に、或人、第一の謠歌を説きて曰く、「其の歌に、『遥遥(ほろほろ)に 言(こと)そ聞(きこ)ゆる 嶋(しま)の藪原(やぶはら)』と所謂ふは、此、宮殿を嶋大臣の家に接ぜて起てて、中大兄、中臣鎌子連と、密に大義を図りて、入鹿を戮さむと謀れる兆なり」といふ。第二の謠歌を説きて曰く、「其の歌に『彼方(をちかた)の 浅野(あさの)の雉(きぎし) 響(とよも)さず 我(われ)は寝(ね)しかど 人(ひと)そ響(とよも)す』と所謂ふは、此上宮の王等の性順くして、都て罪有ること無くして、入鹿が爲に害されたり。自ら報いずと雖も、天の、人をして誅さしむる兆なり。第三の謠歌を説きて曰く、「其の歌に『小林(をばやし)に 我(われ)を引(ひ)きいれ 姧(せ)し人(ひと)の 面(おもて)も知(し)らず 家(いへ)も知(も)らず』と所謂ふは、此入鹿臣が、忽に宮の中にして、佐伯連子麻呂・稚犬養連網田が爲に、誅さるる兆なり」といふ。
岩波文庫 『日本書紀』 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注より
さて、全部読まれましたか?
みっちりと歴史が詰め込まれていたでしょう。
では天智天皇とはいったい誰なのか?あなたにはもうわかったことでしょう。そして天智と鎌足がいかに百済を援助したかったかも。それはなぜだろう?
弟の天武は新羅を重視し、唐を重視した天皇。
ではこの二人は本当に兄弟か?赤の他人では?
飛鳥末期に作られるはずだった天智の朝廷とは、実は?
なぜ不可能に決まっていた百済滅亡を天智と鎌足は助けようとしたのか?それは・・・
天智・鎌足、
逃亡百済王家
だったなら当然のことだったとなりはしないか?
つづく