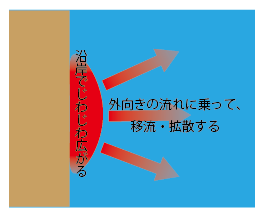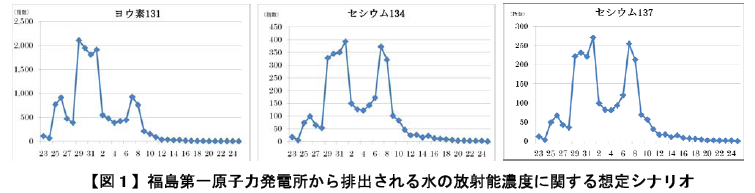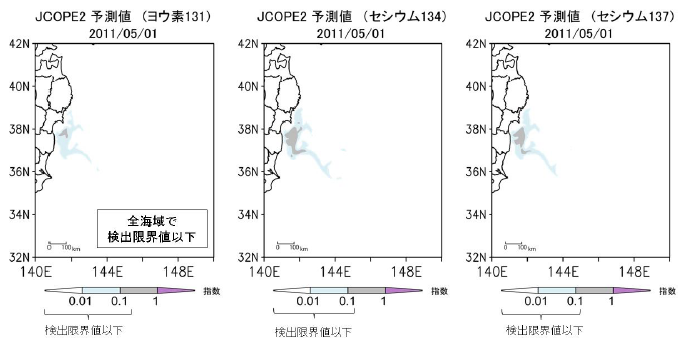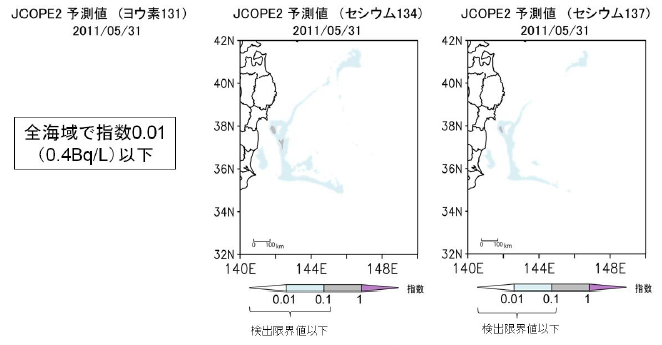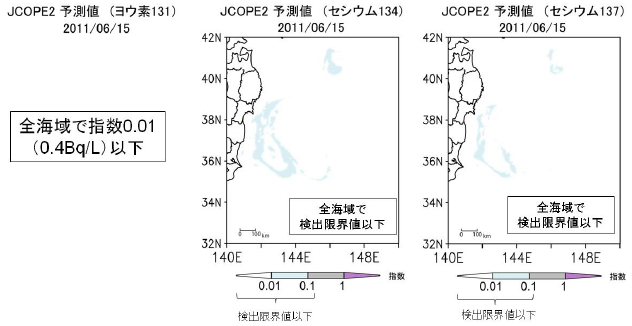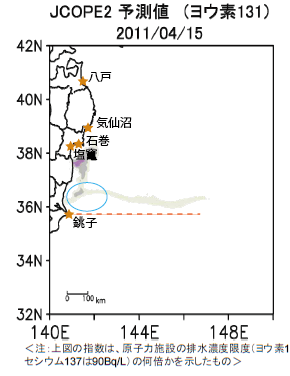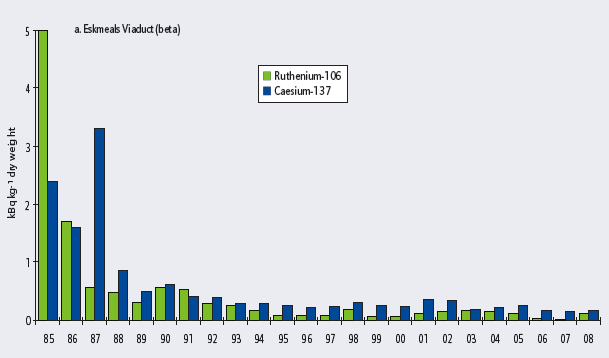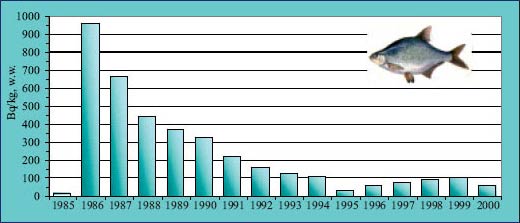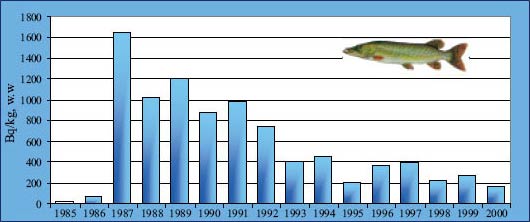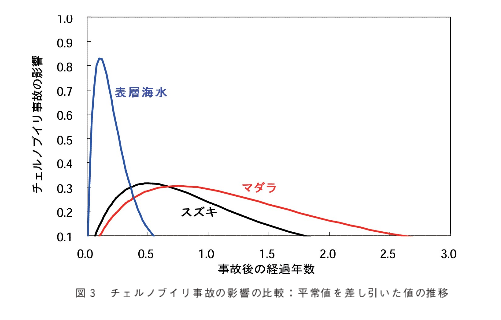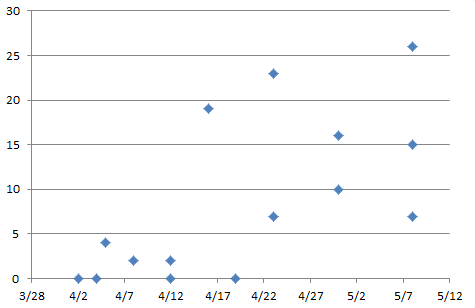福岡県朝倉の高木神社群のひとつ http://www.asahi-net.or.jp/~rg1h-smed/kyusyu1201.htm
このサイトは渡来人研究会。
かわかつ、くくち、わらびて、とらいじんの四人で一昨年いった九州紀行の記事である。
「なるほど英彦山も高木神なのですね。実は昨年、朝倉の旧高木村の地を訪問した際、地元の人と話していると興味あるエピソードを聞きました。その地には都落ちした皇孫が代々居を構えていて「英彦山の宮司が代替わりするときには必ず挨拶に来る慣習があった」と言うものでした。字名にも宮をうかがわせるネーミングが色々残ってるそうです。あまり注目されない山深い集落が高木神を通してて重要な鍵になるのかもしれませんね。」
1記事へのコメントから。実際に高木に行った蕨手(わらびて)氏の言葉。
◆豊前・筑紫地域に集中する高木神社
高木神社 田川郡添田町大字津野6717番の1
高木神社 田川郡添田町落合3583番
高木神社 田川郡添田町津野2227
高木神社 田川郡大任町大行事118番
高木神社 田川郡大任町大行事2496-1
高木神社 嘉麻市熊ヶ畑1075番
高木神社 嘉麻市桑野2588番
高木神社 嘉麻市小野谷1580番
高木神社 嘉麻市桑野1399番
高木神社 嘉麻市平217番
高木神社 久留米市田主丸町豊城1088番
高木神社 宮若市黒丸1572番
高木神社 京都郡みやこ町犀川上伊良原字向田308番
高木神社 京都郡みやこ町犀川下伊良原字荒良鬼1594番
高木神社 築上郡築上町船迫字水上1133番
高木神社 筑紫野市大石字上ノ屋敷569番
高木神社 筑紫野市天山字山畑241番
高木神社 朝倉郡東峰村小石原鼓978-8
高木神社 朝倉郡東峰村宝珠山24番
高木神社 朝倉郡東峰村小石原655番
高木神社 朝倉市佐田377番
高木神社 朝倉市黒川1806番
高木神社 朝倉市黒川3328番
高木神社 朝倉市佐田2953番
高木神社 朝倉市江川1201-1
高木神社 朝倉市杷木白木172番
高木神社 朝倉市杷木赤谷744番
高木神社 朝倉市杷木松末2784番
高木神社 朝倉市須川1683番
※高樹神社 久留米市御井町字神籠石121番
http://rara.jp/kunakoku2/page912
◆肥前高木氏の系譜
「肥前の高木氏について、史料のうえで確実な初見は、寿永二年(1183)十一月に高木氏(藤原朝臣宗家)が大般若免三町を河上社に寄進したことがあげられる。宗家は源平合戦に際しで源氏方に立ち、文治二年(1186)八月、源頼朝から改めて本領である佐嘉郡深溝北郷内甘南備峯の地頭職に補任され(「高城寺文書」)、幕府の御家人となった。建久六年(1195)八月二五日付けの「大友文書」には、肥前国押領使大監藤原宗家(朱書で当国押領使高木大郎大夫)とも見えるが、これは偽文書の疑いがあるといわれる。こうした諸事情によって、高木氏の実質的な先祖は宗家とみることができ、宗家の頃までの高木氏の草創段階が不明であって、系譜の裏付けもないわけである。
2 そもそも、高木氏が何時から佐賀郡高木村に居住したのかという問題がある。
国立公文書館に所蔵の『佐賀諸家系図』下巻の「藤家高木系図」には、高木宗家の祖父の貞永について、「大城三郎大夫」という称号が記載される。貞永の子には高木宗貞、草野永経、北野貞家の三人がいたとされるから、この記載が正しければ、高木氏の起源は意外に新しく、平安後期ないし末期になって初めて、肥前の高木村に遷ってきて住みつき、そこで地名に因り高木氏を名乗ったことになる。
国立公文書館に所蔵の『佐賀諸家系図』下巻の「藤家高木系図」には、高木宗家の祖父の貞永について、「大城三郎大夫」という称号が記載される。貞永の子には高木宗貞、草野永経、北野貞家の三人がいたとされるから、この記載が正しければ、高木氏の起源は意外に新しく、平安後期ないし末期になって初めて、肥前の高木村に遷ってきて住みつき、そこで地名に因り高木氏を名乗ったことになる。
このことを傍証するように、高木一族とされる諸氏は、殆どみな宗貞の後裔に位置づけられる。竜造寺氏については、宗貞の叔父からの分れだが、出自を秀郷流とも称するから別の系譜所伝をもっていた。東高木の八本杉にある高木八幡宮は、久安年中(1145~51)に貞永がはじめて祀るところと伝える。その社記によると、高木越前守貞永が佐賀郡高木庄に下向してきて、夢の中の八幡大神のお告げにより、朝日の昇る像を旗の紋とすべしとされ、同宮を創祀したといわれる。ここでも、高木氏の高木遷住は貞永のときとされるから、貞永ないしは宗貞のときの遷住は、ほぼ信頼してよいのだろう。
貞永についての「大城(おおき)」という呼称は、『和名抄』の筑後国御井郡大城郷の地名に因むものであり、当地は筑後川中流域(北岸と南岸にある)の現久留米市北野町大城あたりとなる。高木氏の有力氏族に於保氏があり、系譜は宗家の甥の於保次郎宗益から始まるとされるが、於保の地名も筑後にあって御原郡於保村(現小郡市北部の大保)ではないかとみられる。大保の東隣の井上に因むとみられる井上氏も、草野支流に見える。なお、於保次郎宗益の弟・尻河六郎宗康の子に平野次郎宗季が見える。
さて、草野も北野も筑後国御井郡の地名であり、とくに草野氏は筑後の在庁官人で在国司・押領使職を世襲した有力な武家であって、系図に宗家の従兄弟と見える草野次郎大夫永平は、『東鑑』文治二年閏七月条にも見える。草野氏はその先祖を天智天皇御宇の草野常門と伝えるから(「草野系図」)、古代から草野を氏としていたことが知られる。他の地の例から見ると、草野は草壁すなわち日下部に通じることが多く、例えば豊前国仲津郡の蒭野(くさの)郷が平安期には草野荘(福岡県行橋市の草野一帯)となり、この地に日下部氏の有力者が居住していた。このことは『本朝世紀』長保元年(999)三月七日条に見えており、記事には蒭野荘の前検校と見える早部信理(法名寂性)は「日下部信理」の誤記と分かる。筑紫では、筑前国には嘉麻郡に草壁郷、筑後国にも山門郡に草壁郷があって、ともに日下部の居住地であったとみられる。
このように、筑後にも筑紫国造一族の日下部君が居たから、草野氏の本姓は日下部(姓は君か宿祢)だったと推せられる。日下部氏は筑紫の有力氏族であったから、大宰府の官人にも見える。寛弘八年(1011)十二月の根岸文書に「権少監日下部」、長和三年(1014)の尊勝院文書に「権掾日下部」、永承七年(1052)の大宰府官連署に「大監日下部」と見えるほか、大宰府の観音寺の牒には、寛弘三年(1006)に「検校少弐藤原、別当大監藤原、少典日下部」とあり、長和元年(1012)八月の文書にも「権少監日下部是高」と見える(『観世音寺古文書』)。こうした事情だから、藤原隆家が権帥として在任した時代の大宰府の官人として日下部氏がおり、それが後に筑後や肥前の在国司職を世襲するなかで、藤原隆家の後裔と称するようになったと推される。
高木八幡宮の上記社記に見るように、草野一族や竜造寺・鍋島・上妻などの諸氏が太陽の昇る様を象った家紋である「日足紋」を用いたのも、その日下部姓出自に因るものとみられる。また、筑紫国造は大彦命の後裔の阿倍氏族と称したから(国造本紀、孝元紀)、これが訛って草野氏の先祖が陸奥から来たとか安倍宗任の後裔ともいわれたことにつながる。 」
http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/takagi.htm
http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/takagi.htm
このように高木は日下部から出る。
その日下部のさらなる派生元をたどるのは、考古学的に可能である。
それは日下部氏が倭五王時代の靫負大伴氏が管理した靫負部(ゆげい・べ)であることが文献上確実なため、そのステータスシンボルである靫(ゆき。靫負軍団が弓矢を入れて背負う道具)を装飾古墳で追いかければよいのである。
京が峰横穴墓群の靫
日田・朝倉から九州山地に沿うように斜めに南下すると球磨川中流の人吉市に到る。ここに大村横穴墳墓群などがあって、それらの壁に靫が彫られている。出発点である朝倉や日田周辺には靫負部の中にあった靱を作る集団靱編部(ゆぎあみ・べ)のステータスである同心円紋=的が描かれる古墳が集中する。
浮羽郡日ノ岡古墳
的は「いくは」とも読み、「いくはのおみ」を探すと大和で大伴氏同族として久米氏とともに、王家の門を弓で守護した記録がある(宮廷いくは門守備的臣)。つまり的臣もまた大伴・膳氏の靫負部のひとりである。これらの記事は大和が九州での倭五王と大伴膳の事跡を取り込み、さも大和の宮殿を彼らが警護したかのように捏造してある(確信ありだが一応うしろに「カモシレナイ」ととけておく)カモシレナイ。しかし日下部氏も大伴氏も膳氏もみな、
九州における「倭王」の警護団である。
人吉こそが日下部の源流である。つまりそこは南九州に多い川上神社信仰のメッカになる。
◆川上神社
この神社群も全国的にあるが熊本・鹿児島が最も多く、川上とは熊襲首魁だった川上タケルのことである。これを「ひじり川上」といい、あるいは大人(おおひと)、弥五郎などと別称する。いわゆる現地先住氏族で抵抗勢力と記紀が書いた熊襲である。
この神社群も全国的にあるが熊本・鹿児島が最も多く、川上とは熊襲首魁だった川上タケルのことである。これを「ひじり川上」といい、あるいは大人(おおひと)、弥五郎などと別称する。いわゆる現地先住氏族で抵抗勢力と記紀が書いた熊襲である。
球磨川沿線はそれらの日下部・川上・熊襲の痕跡と靱のデザインで満ち溢れている。そして例の免田式土器発祥地なのだ。
球磨川へ南下する途上に、幣立宮(へいたてぐう)、猿丸太夫神社(祠)、阿蘇山の古墳群、阿蘇神社、阿蘇国造神社、ストーンサークル、修験の痕跡、石造文化遺跡、石橋、ヤマトタケル景行天皇の巡幸の痕跡、城南町の古墳群、クルソン渓谷、石人、装飾古墳、平家落人伝承地、高木神社、新羅神が神霊スポットのパノラマのように集合している。その線がすべて日田・朝倉、そして田川へと向かうのである。地名山門郡。
この山門郡の地名こそは狗奴国が新天地である近畿で盆地に名づけたものであろうと見える。
筆者は邪馬台国が敵である山門狗奴国そすぐそばにあったと考えてもあながちおかしくないと思う。
というよりも卑弥呼先祖が長江から西九州へ甕棺や水田や横穴墓や銅器を持って西九州三田(神崎郡吉野ヶ里)に入ったあと、
最初に隣接した狗奴国との和合をめざして裏切られた可能性があるからだ。
というよりも卑弥呼先祖が長江から西九州へ甕棺や水田や横穴墓や銅器を持って西九州三田(神崎郡吉野ヶ里)に入ったあと、
最初に隣接した狗奴国との和合をめざして裏切られた可能性があるからだ。
とまれ、
日下部の痕跡はこの道の途中、熊本県高森町の草部(くさかべ)吉見神社に地名を残している。
日下部吉見とは阿蘇神社の系譜では別系統として合流「させられている吉見系日下部氏の系譜である。
草とは熊襲が旅をする人々だったから「旅草」として吉見神社の地名となっている。その吉見神社そばに緒方三郎神社が存在する。三郎は大分の大神氏出身を自称する宇佐神宮の神人(じにん)集団である。彼らは五箇庄平家部落の人々を五木上流へ隠れさせたとなっており、謎の武家集団である。蛇の子孫。
このように日下部が北上して、靫負となりつつ、靱編集団を日田に残し、さらに田川で秦氏に出会ったことから、高句麗渡来人とも合流し高木・鷹栖信仰が生じた。この信仰をそのまま、大和朝廷は置き換えて、アマテラスへつなげたのであろう。そうすることで先住先の王家である狗奴国との大和における正統性を言いたかったのである。
なお、松田聖子という稀代の魔性を輩出した蒲池氏については昨日の1記事の参考サイト文中に言及があるのでここでははぶく。Kawakatu
いずれにせよはっきりしたのは、飛鳥以降の大和朝廷とは九州~瀬戸内~河内を本拠とした倭五王=狗奴国を策謀によって除外し、その信仰もまた名前を変えて皇室系譜としてしまったわけである。
Kawakatu’s HP マジカルミステリーコレクション渡来と海人http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/
画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/
Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html
画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/
Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html