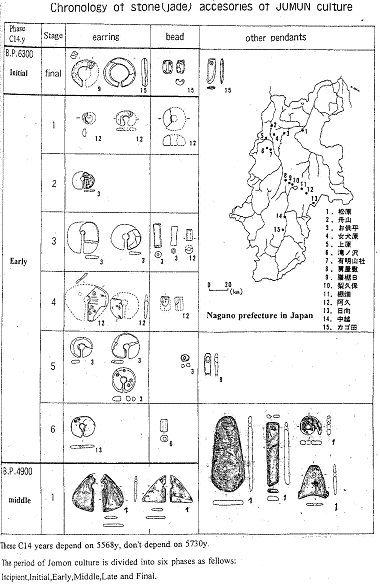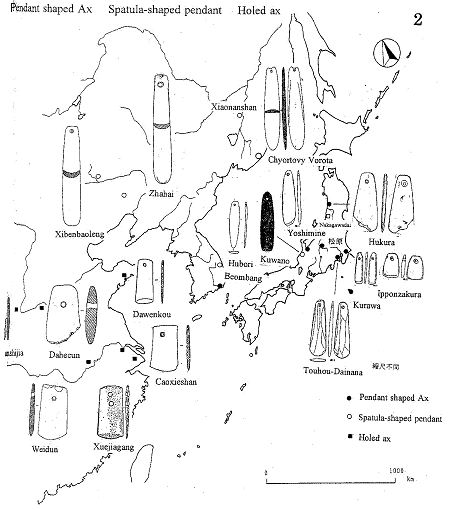今回大作です。じっくり秋の夜長に熟読願いたし。Kawakatu
弥五郎どん・隼人関連地
武雄神社
愛知県知多郡武豊町上ケ12
中央須佐之男命
左 大巳貴命・少彦名命
右 弥五郎殿命(いまたねつぐのみこと・神社でも詳細不明。読み方は大和岩雄氏の指摘から)
長尾七宮・・・大山祗命・豊受姫命・日本武命・菅原道真公・菊理姫命・火結乃命・大物主神
http://ameblo.jp/jicchoku/archive2-201012.html
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.

羽豆(はづ)神社
愛知県知多郡南知多町師崎明神山 1
建稲種命「尾張氏の祖神」
境内社:両皇大神宮、住吉社、春日社、厳島社、月読社、海神社、蛭子社、三狐社、八王子社、天神社、津島社、八幡社
愛知県知多郡南知多町師崎明神山 1
建稲種命「尾張氏の祖神」
境内社:両皇大神宮、住吉社、春日社、厳島社、月読社、海神社、蛭子社、三狐社、八王子社、天神社、津島社、八幡社
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.

※『続日本紀』700年6月3日条、『薩末比売・久売・波豆・衣評督衣君県、助督衣君弖自美、また、肝衝難波、肥人等を従へて、兵を持ちて覓国使刑部真木らを剽劫す。是に竺紫惣領に勅して、犯に准へて決罰せしめたまふ』とあるが、ここに大隅隼人の首魁として巫女の波豆の名がある。読み方は知多半島の突端にある岬・「はず」と同じである。またそのあとの衣評督衣君県は「えのきみ」はこれまた尾張氏の人である(下記石神白龍大王社に詳細)
はず神社・浙江省百越羽人船文銅斧の「羽人」に由来する地名か?
羽津(羽人の出城や軍港)は、伊勢湾各地に点在する。
羽城(名古屋市熱田区伝馬町)、呼続城=羽城(名古屋市南区)、岐阜羽島、羽津城(四日市羽津町)、羽城(碧南市羽根町)、羽豆神社(知多半島師崎)
羽城(名古屋市熱田区伝馬町)、呼続城=羽城(名古屋市南区)、岐阜羽島、羽津城(四日市羽津町)、羽城(碧南市羽根町)、羽豆神社(知多半島師崎)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.

幡頭神社 ( 三河の吉良町宮崎宮前/蛭子岬)
注). 幡頭=幡豆=羽豆=羽頭=羽津とは同意語?
祭神: 建稻種命(第二代尾張国造)
※日本武尊東征の折、海軍を指揮。帰路、海上で遭難し遺体が蛭子岬に漂着。
※羽津(羽人の出城や軍港)は、伊勢湾各地に点在する。
羽城(名古屋市熱田区伝馬町)、呼続城=羽城(名古屋市南区)、岐阜羽島、羽津城(四日市羽津町)、羽城(碧南市羽根町)、羽豆神社(知多半島師崎)
http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/MYBLOG/yblog.html?m=lc&sv=%B1%A9%BF%CD&sk=0
石神白龍大王社
愛知県名古屋市
神紋: 八曜紋 古代の海軍との関わりが?
○八曜紋は、妙見信仰の北斗七星に由来?
※古来、海洋民族は北斗七星を航海の指針として
大洋を移動。
○ご神体の塞石(石神)が幡豆(羽頭)産である。
※大和軍東征の折、海軍の戦闘部隊と輸送
船団の主力は三河であり、名和の船津神社から
成海神社までの浜に集結し出陣した。
愛知県名古屋市
神紋: 八曜紋 古代の海軍との関わりが?
○八曜紋は、妙見信仰の北斗七星に由来?
※古来、海洋民族は北斗七星を航海の指針として
大洋を移動。
○ご神体の塞石(石神)が幡豆(羽頭)産である。
※大和軍東征の折、海軍の戦闘部隊と輸送
船団の主力は三河であり、名和の船津神社から
成海神社までの浜に集結し出陣した。
※衣浦湾を見下ろす入海神社は、東京湾入口の走水海で荒れ狂う海に身を投じた弟橘姫を祭る。
【考察】
塞ぎ石に遠く幡豆産の石を用いた事象に、そこから古代の越(ベトナム)に栄えた東山文化からの流れと、尾張氏創生期の地方国家統一の経緯と深い関係があると推測できる。
①中国の浙江省甲村から出土した羽人船文銅斧の図柄には、頭上に羽根を付けた3名の羽人が櫓走船を操っている。三河の羽頭の語意には、この羽人との関わりが推測できる。
※近くの天竹神社(西尾市)には、崑崙人(天竺人=インド人)渡来(漂着)伝説も残る。
②尾張は、名古屋南部を拠点していた乎止与命が、三河湾を支配していたの海洋民族の娘:真敷刀婢に生ませた建稻種命と、尾張北部の小針田の豪族:大荒田の娘、玉姫との婚姻を成立させた事によって統一された。
http://ohodaka.exblog.jp/7008512/
津島神社
愛知県津島市神明町1
祠官は紀姓堀田氏である。
境内には摂社として弥五郎殿社があり、
祖神武内宿禰と大穴牟遅命を奉斎している。
社伝によると、正平元年(1346)南朝方の忠臣堀田弥五郎正泰が創建したと伝えている。正泰は正平四年に河内四條畷において武家方と戦って戦死した。
系図によれば、京都の八坂神社の執行職を務めた俊全の子俊重が尾張津島天王の祀宮職の始めと記されている。そしてその子重遠が堀田阿波守を称して津島天皇祠官を務め、以後かれの子孫が祠官職を務めた。近世大名の堀田氏も紀姓を名乗り、津島神社祠宮堀田氏の一族といわれている。
Kawakatu注釈
※堀田弥五郎正泰なる人物は歴史上記録は津島神社社伝以外になく、果たして実在の人物かどうか不明である。ほかのサイトもすべてが社伝をそのまま受け売りした記事を書くが、それを疑うものはいないようである。津島神社の名前は、このURLサイトでは、欽明年間に対馬からここへ入った人々が祀るためだという。祭神は牛頭天王とあるのでスサノヲの民間伝承(異説)である蘇民将来つまり全国で言う「山王」「白岳」神であると思われる。
福井を本貫とする織田信長が祖廟とあおいだとあるから、つまりこれは白山信仰である。そして親王伝承も付随するので、間違いなく堀田氏というのは、対馬海人族であり、その素性は紀氏でも実体は推して知ることができる。紀の海民から出たのであろうか?
Kawakatuの民俗古代学的な方程式では貴種流離譚=放浪職能民=渡来or海人となる。
ゆえにこの弥五郎殿が正体を武内宿禰としてあることは、まったく鹿児島の矢五郎どんと同一なので、堀田氏にとってそれは祖神となるのだろう。弥五郎泰なる人物はおそらく伝説的創作人物であると筆者は判断する。これも熊襲・隼人系である。
彌五郎殿
愛知県矢作町字羽城
愛知県矢作町字羽城
十四等級弥五騰社(やごとしゃ)
津島神社より勧請。
元の名は弥五郎殿。
津島神社より勧請。
元の名は弥五郎殿。
この事実は「やはぎ」の矢にも関与する。なぜなら矢作地名は薩摩半島の山・矢筈岳(やはずだけ)に由来する隼人・靫負地名であるからだ。「やはず」とは弓矢の矢の羽側グリップエンドに彫り込まれる弦をかけるための溝である。弓矢製作者地名でもあり、全国に存在する。
熊襲・隼人関連地図
Image may be NSFW.
Clik here to view.![イメージ 5]()
Clik here to view.
カラー●が弥五郎どん祭りのある神社がある地域
(岩川)八幡神社
鹿児島県曽於市大隅町岩川5745
通称岩川八幡(イワガワハチマン)
郷社
御祭神
•玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)
•仲哀天皇(チュウアイテンノウ)
•応神天皇(オウジンテンノウ)
•神功皇后(ジングウコウゴウ)
•武内宿禰命(タケノウチノスクネノミコト)
•伊勢神(イセノカミ)
•保食神(ホショクノカミ)
•春日神(カスガノカミ)
•熊野神(クマノノカミ)
•伊邪那岐神(イザナギノカミ)
•菅原神(スガワラノカミ)
弥五郎どん祭
Image may be NSFW.
Clik here to view.![イメージ 1]()
Clik here to view.
鹿児島・宮崎南部にはほかに数ヶ所弥五郎どん祭りがある神社がある。
その他・三河・尾張・美濃と隼人地名
三河の地域が伊勢神宮に供える幣帛や神衣を準備することや、美濃の南宮神社の境内社だけでなく、近くの養老町などに「隼人・早扉・早戸」などと表記される神社があって、「つわもの」としての隼人の痕跡が認められることを述べた。
実は、このような神社がある地域は古くは「笠の郷」と呼ばれていたとのことで、現在では大垣市上笠から養老町下笠にかけ、栗笠の集落とか笠郷小学校などを含む一帯になる。
「岐阜県の地名」は、この笠の郷や、木曽・長良川沿いの笠神村、笠田村、加佐美山など「笠」のつく地名について、〈美濃国には、現大垣市域の笠毛村・笠木村・笠縫村など、ほかにも笠の字を付けた地名が多い。これらは、慶雲三年(七○六)七月より養老四年(七二○)一○月まで美濃守に任じられた笠朝臣麻呂が任国で開発した村落に笠をつけたものといわれる。〉(同書 二六二頁)
と、笠氏の人である「麻呂」なる人物が、国守として美濃国に貢献した実績が「笠」の地名を生んだとするようである。
笠朝臣麻呂の美濃での活躍はちょうど隼人反乱の時期になるが、七二○年、大隅守・陽候史麻呂殺害事件に対する隼人討伐軍の副将であった笠朝臣御室は麻呂の弟になる。
美濃国の笠という地名が国守笠朝臣麻呂にちなむものであるとすれば、麻呂以前、古く美濃地方に笠氏はいなかったことにもなろう(吉備由来でやってきた)
笠氏については、「瓢箪と縣守」のあと、天智天皇とのかかわりで六四五年に麻呂の父の名が、六六七年には麻呂の叔父の名が載り、次には天武天皇・六八四年の「朝臣の賜姓」のとき、すでに麻呂が笠臣の氏上であったとされるが、他の五十一氏と共に「笠臣」とあるのが記・紀に載る全てである。
笠臣氏
筑紫には、筑紫で没した斉明天皇を弔う観世音寺の建立が、子にあたる天智天皇の発願によってなされていたが未完成のままで残っていた。麻呂は、天智天皇の念願を果たすために筑紫に赴いたことになるが、後に太宰帥として赴任した大伴旅人や、筑前守であった山上憶良などと共に筑紫歌壇を飾る一人となり、この頃、高橋氏とした「薩摩国目高氏」もその歌会に出席していたことになるが、万葉集には麻呂の歌も七首が載る。麻呂は、笠氏の中で最高に名をなした人物のようで、極位は従四位上であった。
万葉集には、笠朝臣金村、笠朝臣子君、笠女郎などの歌も載る。笠女郎は薩摩守として経歴を持つ大伴家持と関係のあった女性の一人であるとされるが、家持への恋情を歌ったなかに、〈詫馬野に 生ふる紫草 衣に染め いまだ着ずして 色に出にけり〉(萬葉集 一 252頁)という歌がある。
この歌の「詫馬野」は、倭名抄の薩摩国高城郡に詫万郷があり、現川内市に遺跡を残す薩摩国府の東北部に比定され、「紫草」は日向・大隅など南九州の特産物として毎年大量に納付された税物であったことが延喜式に載る(式下 92頁)。
笠女郎のこの歌は、薩摩国という共通した環境を二人の男女が互いに経験したことによってのみ理解され、伝えたい思いも更に深まるというもので、笠女郎は家持について来ただけかもしれないが、あるいは笠氏の一人として薩摩国に居住していた可能性もある。
大伴氏や巨勢氏、笠氏が隼人征討軍の指揮者に選ばれたのも、彼らの本貫が南九州にあり、土地の事情を把握していたからに違いない。
笠氏と南九州の関係について、確たる事実は笠朝臣御室の隼人征伐しかないのであるが、笠氏が有木氏と同じく南九州族であれば、美濃の「笠」の名が付く地域に隼人神社があることからも、そこでの麻呂の歴史的な活躍を支えたのは隼人であったと考えられないこともない。
七一四年、木曽路開削の功に対して、笠朝臣麻呂は田六町と使用人に相当するような七○戸を与えられているが、同時に麻呂を助けた門部連、山口忌寸、伊福部君の三氏も位階を進められたり、田を賜っている。
これらの名は、隼人系の人々ではないかと思わせるところがあるが、その一ヶ月半後の記録には、「隼人はくらく荒々しく馴れ親しむ心がなく、未だ憲法もよく知らない。それで、豊前国の民二○○戸を移住させた」などと載るのであった。
とにかく、いかに有能な官僚といえども、協力者がなくてはその能力を発揮することは不可能であり、特にこのころは「氏上」云々などと氏族を単位としてことが運ばれる時代であれば、「笠臣国造」と国造としての伝承はありながら、その国を比定できないということは、あるいは「隼人十一郡」などという特殊な地域に笠氏の本貫があったからではなかったか。
隼人神社のある「笠の郷」一帯は、倭名抄では建部郷や佐伯郷という靫負の存在や、物部郷や富上郷という物部集団の存在をうかがわせる郷が存在する多藝郡のうちにある。
多伎郡とも表記されたこの多藝郡は、日本武尊が東征のあと伊吹山の白猪に化身した山神を侮り、山神の怒りを得て病にかかりこの地に到着したとき、〈今吾が足得歩まず、たぎたぎしく成りぬ〉(記 二二五頁)と、歩行困難になり「たぎたぎしくなった」と言われたので「この地を名づけて当芸という」との地名起源説話がある。
しかし、出雲のあたりの「アタカヤヌシたき姫」と同じく、北薩川内市あたりの古称である高城郡にちなむものであって、隼人神社を中心としたこれらの地域に「弓の名手」として、あるいは「鉄の工人」として古くから隼人が居住し、笠沙の「長」の末裔である笠朝臣麻呂の手足となった可能性は大いにある。
次は、『武芸とか牟下津』とか表記される『武儀(むぎ)の地』が気になるところである。
岐阜郡上八幡は優雅な盆踊りで有名であるが、その八幡町の奥の山々から流れ降る長良川が、谷あいの少し開けた場所に出たところが現在の美濃市から関市となるが、この平野で支流の一つである『武儀川』が合流する。
これら鵜飼が伝えられ、阿多の「長屋」を思わせる長良川の上流域と、その支流武儀川の流域一帯が古代の武儀郡になる。
二二五頁の地図に示したように、古来、美濃紙や関鍛冶で有名なところで、六七二年の壬申の乱では身毛君廣なる人物が天武方の功臣としてあり、雄略天皇のときには、吉備国をけん制するために派遣された身毛君が日本書紀に載り、一帯を取り仕切る一族として身毛氏が繁栄していたようであるが、三河の「衣」地域の猿投神社の祭神でもあった日本武尊の兄・大碓命が始祖とある。
前に、鹿児島県川内市の「麦之浦」に国司原という地名があることなどから、そこに薩摩国の国衙か高城郡の郡衙があった可能性があるとし、「牟木太郎」なる人物が見え、同族らしい「大前」氏の存在も知られることなどから、この地の牟木氏・大前氏を、物部氏系譜に見える麦入宿禰・大前宿禰の親子と同族ではないかとしたのであった。
ここで、更に、美濃の「武芸・身毛」氏の本貫も、あの三河の猿投神社一帯の人々と同じく南九州であって、薩摩高城の「麦・牟木」氏が長良川沿いに拠点を持ちながら、そこの鮎を土地の大神に御食として供していたことから身毛氏と表記されるようになったことを想定してみたいのである。
瓊瓊杵尊の埋葬地として日本書紀に載る「筑紫日向可愛之山陵」は、明治政府によって川内市新田神社裏の亀山に比定されたのであるが、ここに「可愛」の表記が伝わったことは、「可」は古代によく見られる略字であって、正しくは「阿愛」と表記され「あえ」と呼ばれて、神々への饗応を意味する「あえの事」に奉仕する「御食津国」であったのではないか。
つまり、川内市は「大神を阿愛る御食の国」であったもので、「身毛」と表記されたものが訛って「麦」とも表記され、「阿愛」が簡略化され「可愛」と表記されるところとなっているのではないか。
身毛の族人が、大王家の一機構である物部に編成・組み入れられて物部麦入宿禰となり、子の一人は大前宿禰の祖となったが、本貫の薩摩では中世まで勢力を保持し、長良川沿いでは身毛氏・武藝氏となり、あるいは笠朝臣麻呂もその族人としてあった、ということにならないであろうか。
美濃の武藝郡には「笠神」という集落がある。倭名抄での武藝郡生櫛郷とされ、「生櫛」は神前に捧げる斎串を意味すると説くものもある。
その東隣が有知郷で、ここに武儀郡の郡衙はあったとされ、現美濃市の市街域になるようである。すぐ北には「安毛」と書いて「阿多が家」を思わせる「あたげ」と称する村や、「曾代」という村もある。
笠神にある神社には、奈良の葛城鴨の地に祀られ、土佐でも取りあげた阿治志貴高日子根が祭神としてあり、笠神村の北西にそびえる五三八メートルの天王山は、記・紀出雲神話の「國譲り」の前段階で、「葦原中国の平定」のために高天原から派遣された「天若日子」の物語の舞台として伝わる。
ただ、列島上に同族とされる三大勢力が、南九州、山陰、東海にあったが、主導権は南九州勢にあったことをかたる最古層の伝承ではなかったかと想像するだけである。
ここには、弥生時代開始時期の代表的土器とされる遠賀川式土器が出土しているので、古くから海人族の往来があった地域に違いない。
あるいは海人族とするよりも、ここでも鵜飼い漁が特徴的である
その山ぎわに「身毛・笠・宇知」などの名や、記・紀神話にかかわる伝承までも認められることは、この地域が、笠朝臣麻呂などよりはるかに古い時代から、阿多族とかかわりがあったとせざるを得ない≫。
笠臣国造 ( 吉備 )
かさのおみのみやつこ・かさのみやつこ【国造】
[笠臣国造 ( 吉備 )]
笠臣国造(笠国造)とは笠臣国(現・岡山県西部~広島県東部、笠岡市中心)を支配したとされ、国造本紀(先代旧事本紀)によると応神天皇(15代)の時代、元より笠臣国の領主をしていた鴨別命(かもわけのみこと)の8世孫である笠三枚臣(かさみひらのおみ)を国造に定めたことに始まるとされる。鴨別命は御友別の弟で、福井県小浜市の若狭彦神社の社務家である笠氏(笠臣)の祖と言われ、岡山県の吉備中央町にある鴨神社では笠臣(かさのおみ)が祖である鴨別命を祀ったと言われている。新撰姓氏録の笠朝臣(かさのあそみ)の項では、孝霊天皇の皇子・稚武彦命(わかたけひこのみこと)の後裔氏族であり、笠臣は鴨別命の後裔氏族として書かれている。また日本書紀には鴨別命が熊襲征伐の勲功により応神天皇より波区芸県主に封じられたとされているが、波区芸(はくぎ)がどこかは不明である。
http://www.nihonjiten.com/data/263286.html
鴨別
『日本書紀』によると、鴨別は御友別の弟とされる[1]。『日本三代実録』元慶3年(879年)10月22日条では、吉備武彦命の第三男で笠朝臣の祖とする。
また『新撰姓氏録』右京皇別 笠臣条では、鴨別を稚武彦命の孫とする。なお同書では、吉備武彦について稚武彦命の子とする伝承を記すが(右京皇別真髪部条)、それとは別に孫とする異伝も記している(左京皇別下道朝臣条、右京皇別廬原公条)。
『日本書紀』応神天皇22年9月条、『日本三代実録』元慶3年10月条に基づく関係系図
『日本書紀』神功皇后摂政前紀では鴨別は吉備臣祖と見え、熊襲国討伐に遣わされたと記されている.
同書応神天皇22年9月条によると、天皇が吉備に行幸した際に吉備国を分割して吉備臣祖の御友別子孫に封じたといい、この時に鴨別は「波区芸県」(はくぎのあがた:比定地未詳)に封じられたという。
また『新撰姓氏録』右京皇別 笠朝臣条では、応神天皇の吉備行幸の際の伝承として、天皇が加佐米山に登った時に風が吹いて笠が吹き飛ばされたが、これを鴨別命が大猟の前兆であると進言し、果たしてそのようになったので「賀佐」の名を鴨別に下賜したという。
後裔氏族
前述のように、『日本書紀』神功皇后紀では鴨別を吉備臣の祖とし、応神天皇紀では笠臣の祖とする。
また『新撰姓氏録』では、次の氏族が後裔として記載されている。
右京皇別 笠臣 - 笠朝臣同祖。稚武彦命孫の鴨別命の後。
右京皇別 笠臣 - 笠朝臣同祖。稚武彦命孫の鴨別命の後。
国造
『先代旧事本紀』「国造本紀」には、次の国造が後裔として記載されている。
笠臣国造 - 軽島豊明朝(応神天皇)の御世に初めて鴨別命八世孫の笠三枚臣を封じて国造に定める。のちの備中国西部周辺にあたる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E5%88%A5
関連
葦北国造(肥)
葦北国造(肥)
あしきたのくにのみやつこ【国造】
[葦北国造(肥)]
葦北(葦分)国造とは葦北国(現・熊本県水俣市、八代市、葦北郡周辺)を支配したとされ、国造本紀(先代旧事本紀)によると景行天皇(12代)の時代、吉備津彦命(きびつひこのみこと)の子である三井根子命(みいねこのみこと)を国造に定めたことに始まるとされる。国造本紀には葦分と名が記され、また記紀では火葦北国造とも表されているので、火国造の支流とも見られている。
三井根子命後、日奉(ひまつり)部・日奉直・日奉宿禰等を賜姓され、後裔としては達率日羅(にちら)、万葉歌人・日奉部与曽布などが著名である。三井根子命の子・刑部靱負阿利斯登(おさかべのゆけひありしと)は大伴金村によって朝鮮に使わされた国造で、その子・日羅は日本では刑部靱負の職(軍隊の長)、百済では達率(高官の1つ)となり、武人・賢人として知られる。葦北郡津奈木町にある将軍神社は日羅(将軍)を祀っており、逸話も多い。宇土半島にある鴨籠古墳の被葬者は、その棺の大きさから葦北国造の息子と考えられている。
http://www.nihonjiten.com/data/263387.html
葦北(葦分)国造とは葦北国(現・熊本県水俣市、八代市、葦北郡周辺)を支配したとされ、国造本紀(先代旧事本紀)によると景行天皇(12代)の時代、吉備津彦命(きびつひこのみこと)の子である三井根子命(みいねこのみこと)を国造に定めたことに始まるとされる。国造本紀には葦分と名が記され、また記紀では火葦北国造とも表されているので、火国造の支流とも見られている。
三井根子命後、日奉(ひまつり)部・日奉直・日奉宿禰等を賜姓され、後裔としては達率日羅(にちら)、万葉歌人・日奉部与曽布などが著名である。三井根子命の子・刑部靱負阿利斯登(おさかべのゆけひありしと)は大伴金村によって朝鮮に使わされた国造で、その子・日羅は日本では刑部靱負の職(軍隊の長)、百済では達率(高官の1つ)となり、武人・賢人として知られる。葦北郡津奈木町にある将軍神社は日羅(将軍)を祀っており、逸話も多い。宇土半島にある鴨籠古墳の被葬者は、その棺の大きさから葦北国造の息子と考えられている。
http://www.nihonjiten.com/data/263387.html
吉備臣氏
忌部氏と伊部焼き
また、備前は伊部焼(いんべやき・備前焼)と呼ばれる朱泥によるせっ器 (素地がよく焼き締り、吸水性のない焼物。土管・瓶・井戸側・火鉢などの大形物に用いる。)の産地でもある。伊部焼自体の歴史は鎌倉時代以降とされるが、ある程度硬い須恵器は、土師器と違って「窯」を使って焼かれるのだが、その窯跡が総社市奥ヶ谷で見つかっている。その発見によって須恵器窯が備前にが導入されたのは、5世紀中頃になってからのことと考えられているのだ。岡山県備前市伊部という地名にも名を残す伊部は、「斎瓮(いわいべ・いんべ)」で、祭祀に用い、神酒を入れる神聖な甕のことである。「古事記」の孝霊天皇の段に、「大吉備津彦命と稚武吉備津彦命とは、二柱相副ひて、針間の氷河(ひかわ)の前(さき)に忌瓮(いわいべ)を居ゑて、針間を道の口として、吉備国を言向け和したまひき。」とあることからも、古代から、備前で斎瓮が焼かれていたことを物語っていると思う。
また、備前は伊部焼(いんべやき・備前焼)と呼ばれる朱泥によるせっ器 (素地がよく焼き締り、吸水性のない焼物。土管・瓶・井戸側・火鉢などの大形物に用いる。)の産地でもある。伊部焼自体の歴史は鎌倉時代以降とされるが、ある程度硬い須恵器は、土師器と違って「窯」を使って焼かれるのだが、その窯跡が総社市奥ヶ谷で見つかっている。その発見によって須恵器窯が備前にが導入されたのは、5世紀中頃になってからのことと考えられているのだ。岡山県備前市伊部という地名にも名を残す伊部は、「斎瓮(いわいべ・いんべ)」で、祭祀に用い、神酒を入れる神聖な甕のことである。「古事記」の孝霊天皇の段に、「大吉備津彦命と稚武吉備津彦命とは、二柱相副ひて、針間の氷河(ひかわ)の前(さき)に忌瓮(いわいべ)を居ゑて、針間を道の口として、吉備国を言向け和したまひき。」とあることからも、古代から、備前で斎瓮が焼かれていたことを物語っていると思う。
また、「朱泥」というのが「丹土」を思い起こさせて、大変興味深い。「真金吹く」は、「吉備」ともう一つ「丹生」にもかかるのだが、吉備氏の奉斎する神社の鎮座地には、「丹生」や「遠敷(おにゅう)」の地名が見られる。こんなところにも、枕詞の秘密が隠されているのではないか。
このように吉備氏は、作金者(かなだくみ)としての賀茂氏・息長氏、土器製作としての和邇氏・越智氏の両面を兼ね備えており、岡山県総社市新本(しんぽん)の国司(くにし)神社には、全国で三ヶ所だけの「赤米神事」も残っている。そして、四道将軍も遣唐使も陰陽師も出している。当に、典型的な海人族と言えるのではないだろうか
http://homepage2.nifty.com/amanokuni/kibi.htm
<奉祀する神社>
吉備津彦神社(岡山市一宮) ※備前国一の宮
祭神&祖神 大吉備津彦命(比古伊佐勢理毘古命)
社家 吉備氏
祭神&祖神 大吉備津彦命(比古伊佐勢理毘古命)
社家 吉備氏
吉備津神社(岡山市吉備津)
祭神&祖神 大吉備津彦命、倭迹迹日百襲姫命、稚武吉備津彦命、御友別 他
社家 吉備氏
祭神&祖神 大吉備津彦命、倭迹迹日百襲姫命、稚武吉備津彦命、御友別 他
社家 吉備氏
若狭彦神社(福井県小浜市、上社は龍前、下社は遠敷) ※若狭国一の宮
祭神 上社:若狭彦神(彦火火出見尊)、下社:若狭姫神(豊玉毘売命)
遠敷明神・白石大明神とも
祖神 鴨別命
社家 笠氏
祭神 上社:若狭彦神(彦火火出見尊)、下社:若狭姫神(豊玉毘売命)
遠敷明神・白石大明神とも
祖神 鴨別命
社家 笠氏
備中吉備津神社(岡山市吉備津)
祭神 大吉備津彦命、千千速比売命、倭迹迹日百襲姫命 他
祖神 大吉備津彦命
社家 賀陽氏
剣神社(福井県丹生郡織田町) ※越前国二の宮
祭神 素戔嗚尊、気比大神、忍熊王(都留伎日古命)
神功皇后摂政十三年、忍熊王の創建と伝えられる。継体天皇の三国、気比神宮(越前国一の宮)にも、非常に近い地理関係だというのが興味深い。
祭神 素戔嗚尊、気比大神、忍熊王(都留伎日古命)
神功皇后摂政十三年、忍熊王の創建と伝えられる。継体天皇の三国、気比神宮(越前国一の宮)にも、非常に近い地理関係だというのが興味深い。
剣神社という名の神社は福井県に多く、山口県・徳島県・鹿児島県などに分布しているが、祭神は、素戔嗚尊、倭建命、経津主命、安徳天皇とまちまちである。
滋賀県大津市の瀬田で死んだはずの忍熊王の、その後の消息を伝えるのがこの剣神社である。
社伝は、「神功皇后13(873)年2月、忍熊王は都を去って越の国に入り、角鹿(敦賀)の海を渡って梅浦に着き、当地を害する梟賊を討伐せんとして霊夢を見、息長氏系の五十瓊敷入彦命(いにしきのいりひこのみこと・11代垂仁天皇の第一皇子。
母は日葉酢媛命。倭比売の兄。)が鳥取川上宮(大阪泉南郡阪南町)で作った剣を、伊部臣が座ヶ嶽の山頂に祀っていたものを得て、賊を平定。
忍熊王は、神剣を素戔嗚尊の御霊代として斎き祀り、この地に社を設けた。後、郷民が忍熊王の偉業を称え、都留伎日古命(つるぎひこのみこと)として慕い奉り、父神の気比大神と共に配祀した。」と伝えている。
この場合の父神は忍熊王の父の仲哀天皇を指すと思うが、気比大神の伊奢沙和気(いざさわけ)の名は、息長氏の祖・天之日矛の神宝「胆狭浅(いざさ)の太刀」から来ているといい、元来は「剣の神」であったと思われる。気比大神は、素戔嗚尊の神剣「草薙剣」を賜った、倭建命ではなかったか? 祭神の一人、素戔嗚尊が八俣大蛇を切った「天羽斬剣」は、冒頭に述べた通り吉備の地にあるとも言われ、興味は尽きない。
因みに、織田信長の「織田」姓もこの丹生郡織田の地名から来ており、信長は越前平定の後、一族の氏神として神社の保護に尽力している。
白山神社(石川県鶴来町)
祭神 菊理媛神(白山比大神)、伊弉諾尊、伊弉冉尊
祖神 上道保命
社家 上道氏
社家は吉備上道臣の裔というが、確証はない。とはいうものの、白山の開祖である泰澄は海人系(秦氏)だし、阿倍氏の氏寺の文殊院も菊理媛神を鎮守としていることなどから、可能性は高いと思う。
祭神 菊理媛神(白山比大神)、伊弉諾尊、伊弉冉尊
祖神 上道保命
社家 上道氏
社家は吉備上道臣の裔というが、確証はない。とはいうものの、白山の開祖である泰澄は海人系(秦氏)だし、阿倍氏の氏寺の文殊院も菊理媛神を鎮守としていることなどから、可能性は高いと思う。
気比神宮(福井県敦賀市曙町) ※越前国一宮
祭神 伊奢沙別命(気比大神・御食津神)
仲哀天皇、神功皇后、日本武尊、応神天皇、玉妃命、武内宿禰
祖神 大吉備津彦命
社家 角鹿氏・鶴岡氏
祭神の関係で息長氏に入れたが、創建当初の社家は、角鹿国造家の角鹿氏だったと思われる。その証拠に、大吉備津彦命の5世孫、角鹿玉手という人が「角鹿神祭」を勤めており、その子孫の多くも「大神禰宜」を勤めている。
祭神 伊奢沙別命(気比大神・御食津神)
仲哀天皇、神功皇后、日本武尊、応神天皇、玉妃命、武内宿禰
祖神 大吉備津彦命
社家 角鹿氏・鶴岡氏
祭神の関係で息長氏に入れたが、創建当初の社家は、角鹿国造家の角鹿氏だったと思われる。その証拠に、大吉備津彦命の5世孫、角鹿玉手という人が「角鹿神祭」を勤めており、その子孫の多くも「大神禰宜」を勤めている。
<有名人>
大吉備津彦命(おほきびつひこのみこと・吉備津彦命)
五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)
7代孝霊天皇と意富夜麻登玖邇阿礼比売命(おおやまとくにあれひめ・倭国香媛)の子。倭迹迹日百襲姫命の弟。
五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)
7代孝霊天皇と意富夜麻登玖邇阿礼比売命(おおやまとくにあれひめ・倭国香媛)の子。倭迹迹日百襲姫命の弟。
四道将軍(記紀伝承で、10代崇神天皇の時、四方の征討に派遣されたという将軍。北陸は大彦命、東海は武渟川別命、西道(山陽)は吉備津彦命、丹波(山陰)は丹波道主命)。
記紀には母の出自はないが、名に「おほやまと」「やまと」とあるので、倭・大倭氏と思われる。因みに、孝霊天皇の祖母(孝昭天皇皇后)は、尾張氏の世襲足媛(よそたらしひめ)である。神武から開化までの和風謚号に、「倭」や「大倭」が付くことが多い。存在を否定された闕史八代の天皇ではあるが、この辺の天皇を祖とする海人系の氏族は多いのである。内膳を勤めた者が多いところからも、推測できると思う。
この方の子供には、日奉部氏(火葦北国造家)の祖の三井根子命と、日下部君の祖といわれる大屋田根子命がいる。
倭迹迹日百襲姫命(やまととびももそひめのみこと)
大吉備津彦命の姉。
箸墓の主と言われ、天照大神や卑弥呼だという説もある。大物主の妻で、夫の正体である蛇の姿を見て、箸で陰部を突いて亡くなったとされる、巫女的な皇女。
大物主の妻といえば、越智氏の勢夜陀多良比売である。陰部を突いてという亡くなり方は、誓約に勝ち誇った素戔嗚尊が、斑馬の皮を逆剥ぎにして忌服屋(神御衣を織る神聖な機殿)に投げ込んだ際、天照大神自身、又は稚日女尊(生田神社祭神、天照大神の幼名ともいう)、又は機織女が、梭(緯糸を通す操作に用いる、織機の付属具。)で陰部を突いたという記載と似ている。斎機殿に籠って機を織るというのは神妻としての巫女の表現で、木花之開耶媛命も機織をしていた。
大吉備津彦命の姉。
箸墓の主と言われ、天照大神や卑弥呼だという説もある。大物主の妻で、夫の正体である蛇の姿を見て、箸で陰部を突いて亡くなったとされる、巫女的な皇女。
大物主の妻といえば、越智氏の勢夜陀多良比売である。陰部を突いてという亡くなり方は、誓約に勝ち誇った素戔嗚尊が、斑馬の皮を逆剥ぎにして忌服屋(神御衣を織る神聖な機殿)に投げ込んだ際、天照大神自身、又は稚日女尊(生田神社祭神、天照大神の幼名ともいう)、又は機織女が、梭(緯糸を通す操作に用いる、織機の付属具。)で陰部を突いたという記載と似ている。斎機殿に籠って機を織るというのは神妻としての巫女の表現で、木花之開耶媛命も機織をしていた。
稚日女尊を祀る生田神社の初代祝は、弟の五十狭芹彦命と名前の似ている五十狭茅宿禰の子、海上五十狭茅である。この符合、何か隠されているように思うのだが????
稚武吉備津彦命(わかたけきびつひこのみこと・稚武彦命)
7代孝霊天皇と、意富夜麻登玖邇阿礼比売命の妹の蝿伊呂杼(あえいろど)の子。
大吉備津彦命の異母弟であり、従兄弟。
7代孝霊天皇と、意富夜麻登玖邇阿礼比売命の妹の蝿伊呂杼(あえいろど)の子。
大吉備津彦命の異母弟であり、従兄弟。
針間之伊那毘能大郎女(はりまのいなびのおおいらつめ)
稚武吉備津彦命の娘。12代景行天皇の妃で、櫛角別王(くしつぬわけのみこ)、大碓命(おおうすのみこと)、小碓命(をうすのみこと・倭建命)、倭根子命(やまとねこのみこと)、神櫛王(かみくしのみこ)を産んだ。
稚武吉備津彦命の娘。12代景行天皇の妃で、櫛角別王(くしつぬわけのみこ)、大碓命(おおうすのみこと)、小碓命(をうすのみこと・倭建命)、倭根子命(やまとねこのみこと)、神櫛王(かみくしのみこ)を産んだ。
因みに景行天皇の母は、息長氏の丹波道主命の娘、日葉洲媛命である。
倭建命・日本武尊(やまとたけるのみこと)
小碓命(をうすのみこと)
息長氏系12代景行天皇と針間之伊那毘能大郎女の皇子。
父の景行天皇が美濃国造の大根王(おおねのみこ)の娘、兄比売・弟比売の姉妹を召されようとしたところ、兄の大碓命が横取りした上、天皇との朝夕の会食にも顔を出さなくなった。天皇は小碓命を使いに出して詰問させることにしたが、小碓命は兄を捕えて手足をもいで殺した上に薦に包んで投げ捨ててしまった。天皇は小碓命の乱暴を恐れ、またその力を生かすために熊襲征伐を申し付けた。叔母の倭比売命(母方が息長氏)に衣装をもらった命は、女装して熊襲の宴席に潜り込み、熊襲兄弟を首尾よく刺し殺した。この時瀕死の弟建は命に敬服して、「倭建」の名を献じたという。命はさらに「山神、河神、穴戸神を言向け和し」、最後に出雲建を打ち倒して都へ凱旋する。
小碓命(をうすのみこと)
息長氏系12代景行天皇と針間之伊那毘能大郎女の皇子。
父の景行天皇が美濃国造の大根王(おおねのみこ)の娘、兄比売・弟比売の姉妹を召されようとしたところ、兄の大碓命が横取りした上、天皇との朝夕の会食にも顔を出さなくなった。天皇は小碓命を使いに出して詰問させることにしたが、小碓命は兄を捕えて手足をもいで殺した上に薦に包んで投げ捨ててしまった。天皇は小碓命の乱暴を恐れ、またその力を生かすために熊襲征伐を申し付けた。叔母の倭比売命(母方が息長氏)に衣装をもらった命は、女装して熊襲の宴席に潜り込み、熊襲兄弟を首尾よく刺し殺した。この時瀕死の弟建は命に敬服して、「倭建」の名を献じたという。命はさらに「山神、河神、穴戸神を言向け和し」、最後に出雲建を打ち倒して都へ凱旋する。
ところが天皇は矢継ぎ早に東国への遠征を命じたので、命はまたもや叔母の倭比売命を訪ねて、天叢雲剣(草薙剣)と火打石の入った袋を貰って、気を取り直して出発。相模国造に騙された時には、この剣と火打石が命の窮地を救う。また、走水(はしりみず)の海では暴風雨に巻き込まれが、妃の弟橘比売(穂積氏の忍山宿禰の娘)が入水して嵐の神を鎮め、命の危難を救った。
安房・甲斐・信濃を経て尾張に至り、妃の美夜受比売(尾張氏)のところに剣を置いて、伊吹山の神の平定に向かったが、山の神の毒気にあたって瀕死の状態となり、能煩野(三重県鈴鹿市)で天皇の坐す都を偲びながら、永遠の旅路に入られたという。
倭建命の魂は大白鳥となって天翔け、妃や御子たちはその白鳥を追いながら四首の歌を詠み、この歌は天皇の御大葬の時に歌うのである、と「古事記」は伝える。
倭建命は、多くの海人系の女性を妃としている。弟橘比売は穂積氏、美夜受比売は尾張氏、布多遅比売は息長氏系の水穂之真若王の子孫、大吉備建比売は吉備氏である。何度も助けてくれる叔母の倭比売命も息長氏系だし、母親の分からない御子に息長田別王(おきながたわけのみこ)という方もいらっしゃる。倭建命の遠征は海人族を傘下に組み入れる為のものだったといえるだろう。
息長帯比売(神功皇后)の夫、14代仲哀天皇は倭建命の子だが、倭建命の弟、13代成務天皇には、穂積氏の女性を母に持つ和訶奴気王(わかぬけのみこ)という男子がいるにもかかわらず、何故に皇位は仲哀が継いだのか? この王の名は古事記にしかなく、日本書紀には「成務天皇の子に、男子がなかった」としている。和訶奴気王は早世したのかもしれないが、書紀のボカシ方が気になるところだ。
吉備武彦命(きびのたけひこ・吉備臣日子・大吉備建日子)
稚武吉備津彦命の子、大吉備津彦の甥。
倭建命が東征する際、12代景行天皇が随行させた副官。
稚武吉備津彦命の子、大吉備津彦の甥。
倭建命が東征する際、12代景行天皇が随行させた副官。
大中津比売命(おおなかつひめのみこと)
日子人之大兄王の娘、伊那毘能若郎女の孫。14代仲哀天皇の妃。
15代応神と帝位を争った、忍熊王(おしくまのみこ)と、香坂王(かごさかのみこ)の母である。
日子人之大兄王の娘、伊那毘能若郎女の孫。14代仲哀天皇の妃。
15代応神と帝位を争った、忍熊王(おしくまのみこ)と、香坂王(かごさかのみこ)の母である。
忍熊王(おしくまのみこ)
14代仲哀天皇と、大中津比売命(おおなかつひめのみこと)との第一皇子。
神功皇后が三韓遠征から凱旋して戻ってくる時、弟の香坂王と共に、なんで弟の誉田別尊に従えるかと、吉師の先祖の五十狭茅宿禰と、和邇氏と同族と言え、なんと政敵の応神の息長氏の水穂之真若王の子孫で犬上君の先祖の倉見別(くらみわけ)を将軍として、東国の兵を起こさせた。武内宿禰と和邇氏の難波根子建振熊命が率いる軍に、完全な騙し討ちで敗れ、腹心の五十狭茅宿禰と共に、近江(滋賀県大津市)の瀬田の渡りで入水自殺した。数日後、遺体は下流の宇治川で発見されたという。
14代仲哀天皇と、大中津比売命(おおなかつひめのみこと)との第一皇子。
神功皇后が三韓遠征から凱旋して戻ってくる時、弟の香坂王と共に、なんで弟の誉田別尊に従えるかと、吉師の先祖の五十狭茅宿禰と、和邇氏と同族と言え、なんと政敵の応神の息長氏の水穂之真若王の子孫で犬上君の先祖の倉見別(くらみわけ)を将軍として、東国の兵を起こさせた。武内宿禰と和邇氏の難波根子建振熊命が率いる軍に、完全な騙し討ちで敗れ、腹心の五十狭茅宿禰と共に、近江(滋賀県大津市)の瀬田の渡りで入水自殺した。数日後、遺体は下流の宇治川で発見されたという。
吉備御友別(きびのみともわけ)
吉備武彦の子。
15代応神天皇が吉備に行幸された際、膳夫として饗を供した。その功績で、一族が分封に与る。
吉備武彦の子。
15代応神天皇が吉備に行幸された際、膳夫として饗を供した。その功績で、一族が分封に与る。
吉備兄媛(きびのえひめ)
御友別の妹。15代応神天皇の妃である。
吉備の父母を恋しがったので、応神が淡路の三原の海人八十人を水手として、吉備に里帰りさせた。因みに淡路は阿曇氏の本拠の一つである。兄の功績に肖って織部を賜っている。記紀の時代、吉備にはその子孫らがまだいたと記載がある。
この姫の記述は「書紀」のみで「記」にはなく、倭氏の黒日売の記述が、天皇が一代違うが「記」のみにあることから、この吉備兄媛と黒日売は同一人物であろうと言われている。応神・仁徳同一人物説の根拠の一つとなっている説話である。
御友別の妹。15代応神天皇の妃である。
吉備の父母を恋しがったので、応神が淡路の三原の海人八十人を水手として、吉備に里帰りさせた。因みに淡路は阿曇氏の本拠の一つである。兄の功績に肖って織部を賜っている。記紀の時代、吉備にはその子孫らがまだいたと記載がある。
この姫の記述は「書紀」のみで「記」にはなく、倭氏の黒日売の記述が、天皇が一代違うが「記」のみにあることから、この吉備兄媛と黒日売は同一人物であろうと言われている。応神・仁徳同一人物説の根拠の一つとなっている説話である。
鴨別命(かものわけのみこと)
御友別の弟。若狭彦神社社務家である笠氏の租。
神功皇后の熊襲征伐の際、最初に派遣されて熊襲を討った。
御友別の弟。若狭彦神社社務家である笠氏の租。
神功皇后の熊襲征伐の際、最初に派遣されて熊襲を討った。
笠県守(かさのあがたもり)
笠氏の系図によれば鴨別命の7世孫だが、鴨別命は御友別の弟なので時代が合わない。たぶん鴨別命の息子であろう。
16代仁徳天皇紀、吉備中国の川島河の川股に竜がいて、毒を吐いて人々を苦しめていたのを、瓢を用いて退治した話が載っている。瓢(ひさご)は水の呪術に関係が深く、神功皇后なども用いている。尚、天・光の枕詞「ひさかた」は、「ひさご形」だという説がある。
笠氏の系図によれば鴨別命の7世孫だが、鴨別命は御友別の弟なので時代が合わない。たぶん鴨別命の息子であろう。
16代仁徳天皇紀、吉備中国の川島河の川股に竜がいて、毒を吐いて人々を苦しめていたのを、瓢を用いて退治した話が載っている。瓢(ひさご)は水の呪術に関係が深く、神功皇后なども用いている。尚、天・光の枕詞「ひさかた」は、「ひさご形」だという説がある。
吉備下道臣前津屋(きびのしもつみちのおみさきつや)
21雄略天皇の時、天皇と自分に見立てた鶏や女を戦わせたとして、不敬の罪で誅殺されている。この時、同族70人も連座させられている。
21雄略天皇の時、天皇と自分に見立てた鶏や女を戦わせたとして、不敬の罪で誅殺されている。この時、同族70人も連座させられている。
吉備上道臣田狭(きびのかみつみちのおみたさ)
御友別の曾孫。稚媛という美しい妻があり二人の男子をもうけていたが、21代雄略天皇がその美貌を聞き及んで、田狭を任那の国司に赴任させた上、稚媛を召してしまった。それを知った田狭は、任那から日本と仲の悪い新羅へ亡命しようとするが、雄略は更に意地の悪いことに、田狭と稚媛の息子の弟君を征新羅将軍に任命してしまう。出撃したものの困った弟君は、風待ちと称して大島に留まって月日を重ねた。そこへ父の使いが来、謀叛の計画を伝えるが、発覚を恐れた妻樟媛によって殺されてしまう。
御友別の曾孫。稚媛という美しい妻があり二人の男子をもうけていたが、21代雄略天皇がその美貌を聞き及んで、田狭を任那の国司に赴任させた上、稚媛を召してしまった。それを知った田狭は、任那から日本と仲の悪い新羅へ亡命しようとするが、雄略は更に意地の悪いことに、田狭と稚媛の息子の弟君を征新羅将軍に任命してしまう。出撃したものの困った弟君は、風待ちと称して大島に留まって月日を重ねた。そこへ父の使いが来、謀叛の計画を伝えるが、発覚を恐れた妻樟媛によって殺されてしまう。
稚媛は雄略との間に磐城皇子と星川稚宮皇子を産んだが、天皇を憎んでいたのだろう、雄略が死ぬと、息子星川皇子に帝位を狙う様に諭し、大蔵の役所を占拠させるが、力及ばす包囲され、稚媛、異父兄の兄君(田狭の長男)と共に焼死してしまう。吉備上津道臣らは、星川皇子を救おうと軍船四十艘を率いて海上をやって来たが、間に合わなかったという。
こうしてみると、暴れん坊雄略天皇は吉備臣を目の仇にしている。それは彼らが元々、帝位を狙える家柄にあったからではないのか?
賀陽采女(かやのうねめ・若媛とも)
御友別の9世孫。34代舒明天皇の采女。三島真人の祖となる賀陽皇子を産む。
大海人皇子という名から、天武天皇を賀陽皇子と同一人物であるとする説もある。しかしながら、天智・天武・賀陽皇子らの父、舒明天皇の謚号は「息長足日広額尊」であり、息長真手王の娘、広姫の孫にあたる海人系の天皇である。天武の和風謚号にも「瀛(おき)」の字が入っており、息長氏系の壬生(乳部)がついていた可能性もある。
賀陽氏はこの賀陽采女(若媛)の祖父、賀陽高室に始まる備中吉備津神社の社家であるが、その五代前の御友別の子、仲彦が既に賀陽国造になっている。「賀陽」は岡山県上房郡賀陽町にその名を残すが、「加悦」とするならば加羅(伽耶)つまり任那のことであり、天之日矛との関連が想像される。
吉備真備(きびのまきび)
奈良時代の官人・文人・陰陽師。717年(養老1)遣唐留学生として入唐、735年(天平7)帰国。「唐礼」「大衍暦経」などを将来。橘諸兄に重用されたが、のち九州に左遷。その間、遣唐副使として再び渡唐。恵美押勝の乱平定に貢献。従二位右大臣に累進。世に吉備大臣という。著「私教類聚」「刪定律令」など。(695?~775)
奈良時代の官人・文人・陰陽師。717年(養老1)遣唐留学生として入唐、735年(天平7)帰国。「唐礼」「大衍暦経」などを将来。橘諸兄に重用されたが、のち九州に左遷。その間、遣唐副使として再び渡唐。恵美押勝の乱平定に貢献。従二位右大臣に累進。世に吉備大臣という。著「私教類聚」「刪定律令」など。(695?~775)
海人系の陰陽師としては、他に、安倍晴明、津守連通などが有名。
真備の前年に16歳で唐に渡った安倍仲麻呂と、交友関係にあったと思われる。阿倍氏も吉備氏も海人系であり、陰陽師を多く排出しているところにも共通点がある。また、阿倍氏の陰陽道の師匠筋にあたる賀茂氏にも、大宝元(701)年に遣唐使中佑として唐に渡った賀茂朝臣吉備麻呂(きびまろ)という人がいる。賀茂氏には「吉備」と名前に付く人が多く、賀茂姓は吉備氏が孝謙女帝(阿倍内親王)の時代に賜ったという説もあって、大変面白い。陰陽道の道教的思想は、彼らが伝えたのであろうか。それとも、海人の血ゆえに既に土壌があったのか?
「今昔物語」に、聖武天皇(藤原宮子の子)に一夜の寵を受けた女性が黄金千両を貰い、程なく亡くなったが、その女性が葬られた石淵寺に悪霊が出て、寺に参った者は一人として生きて帰ることがなくなってしまった。陰陽道に通じていた吉備大臣が石淵寺に行って悪霊に会ってみると、悪霊は、「自分の墓に黄金を埋めた罪で蛇身の罪を受け苦しんでいるので、墓を掘って、黄金の半分で法華経を写して供養し、残りの半分はあなたの財として下さい。」と言う。墓を掘ってみると黄金を入れた壺があり、大蛇がとぐろを巻いていた、という話が載っている。
蛇が法華経で成仏するというのは「小夜比売草紙」に関係があり、黄金と蛇の構図は、八百比丘尼や朝日長者の埋蔵金伝説にも関係する。
和気清麻呂(わけのきよまろ)
奈良時代の官人。本姓、吉備磐梨別公(きびのいわなすわけのきみ)。備前出身。
道鏡が宇佐八幡の神官と結託して皇位を望んだ時、藤原一族の意を請けて、勅使として宇佐八幡の神託を受け、阻止。ために道鏡の怒りを買い、名を別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と改めて大隅に流されたが、道鏡失脚後召還されて、光仁・桓武天皇に仕え、平安遷都に尽力。民部卿・造宮大夫・従三位。護王神社に祀る。(733~799)
奈良時代の官人。本姓、吉備磐梨別公(きびのいわなすわけのきみ)。備前出身。
道鏡が宇佐八幡の神官と結託して皇位を望んだ時、藤原一族の意を請けて、勅使として宇佐八幡の神託を受け、阻止。ために道鏡の怒りを買い、名を別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と改めて大隅に流されたが、道鏡失脚後召還されて、光仁・桓武天皇に仕え、平安遷都に尽力。民部卿・造宮大夫・従三位。護王神社に祀る。(733~799)
吉備磐梨別公の祖は、阿倍氏系11代垂仁天皇の子孫で、吉備磐梨別意富己自(おおこじ)という。越智氏の冒頭で述べたとおり、伊予の御村別氏の祖は、息長氏系の12代景行天皇と阿倍氏の高田媛の子、武国凝別皇子(くにこりわけのみこと)で倭建命の異母兄弟にあたり、倭建命と大吉備建比売の子、十城別王(とおきわけのみこ)が伊予別(いよわけ)君の祖で、両氏は後に「和気氏」を名乗っている。景行天皇は垂仁天皇の子であり、備前出身というのを重要視して、異論もあろうが和気氏を吉備氏系としてみた。
http://homepage2.nifty.com/amanokuni/kibi.htm
ここまですべて引用。
以下、Kawakatuの考証
以上、各種サイトをランダムに、弥五郎関連から始めていった結果、最終的には吉備臣と熊襲と葦北国造にたどり着けた。また吉備臣氏笠臣からは物部、尾張、和邇、忌部、春日、息長、葛城鴨などの大和地方初期から入っていた氏族が関連性が深いことも見えてきた。これらの氏族が熊襲・隼人ら南九州氏族との深い因縁を持つことも見えてきた。さらに武内宿禰=黒尾神としての弥五郎どんの性格も見えた。
また愛知県の知多半島一帯という尾張氏の版図にある武雄に、なぜか弥五郎殿が別の読み方で祭られていたのはしてやったりであった。しかし残念なことに多氏だけはなぜかこれらの詳しいサイト情報にはからんでこなかった。やはり多氏は謎であり、古代史を解きほぐすための鍵である。しかしその資料はまったくない。太安万侶が『古事記』を編纂したこと、その父・多品治が岐阜三野にいた騎馬軍団であったが、その「ほむじ」の名は、どうも「ほむじわけ・白鳥伝説」との関係があるのではないかという着想を得られただけである。「ほむち」「わけ」の名はやはり吉備の「わけ」から出るのではあるまいか?また「ほむち」は応神天皇の「ほむた」とも相にていることも、吉備の祭祀遺物が纏向から出ることと合わせて、どうやらこれらの氏族すべての連合体としての邪馬台国女王の担ぎ上げが起きたことを匂わせるとの感をいよいよ強くしたのだった。
やはり多氏は日本古代史の何か琴線に触れるようなところを握っている。だから安麻呂も、「多氏『古事記』」の肝の部分を明確に書けなかった、あるいは改竄された可能性がある。