環日本海の玉文化の始源と展開 2.「東アジアにおける玦状耳飾をはじめとする装身具セットの起源と展開」
川崎 保
(財)長野県文化振興事業団
長野県埋蔵文化財センタ 調査研究員
(財)長野県文化振興事業団
長野県埋蔵文化財センタ 調査研究員
玦状耳飾研究はすでに多くの研究史がある。とくにその起源についでは大陸起源説と日本列島自生説の二つに大別できる。大陸起源説ではおもに江南地方起源説が有力であったが、近年では中国東北やロシア沿海州などの北方起源説が注目されてきている。
筆者はとくに玦状耳飾だけでの研究ではいわゆる「他人の空似」という日本列島自生説の批判をかわせないと考えていて、これを克服するためにも玦状耳飾と同様な玉質の石材で作られている装身具をセットとして合わせて研究することによって、大陸起源説と日本列島自生説のいずれがより合理的であるか、また大陸起源説であれば、どこのどういう文化の影響のもとに日本列島の玦状耳飾をはじめとする石製装身具のセットが成立したかを考えている。
日本列島で玦状耳飾が出現した段階(縄文時代早期末)にすでにこれに管玉や垂飾がセットとして伴っていることがわかってきている。縄文時代早期末の玦状耳飾はほぼ円形で中央孔が大きく、孔側は比較的扁平なドーナツ形(浮輪形)のもの(藤田富士夫のいう「環状型」)である。垂飾は、まだ類例は少ないが、箆状垂飾もこのセットの一つであった可能性が高い。
東アジアの中でこのセットを比較してみると、ロシア沿海州の早期新石器時代のルドニンスカヤ文化に属するチョール夕ヴィ・ヴフロータ洞穴、中国黒龍江省小南山遺跡や興隆窪文化に属する遼寧省査海遺跡などにもこのセットが見られる。
とくに箆状垂飾(中国ではヒ状器)は、おもに中国華北以北でしか見られないものである。またロシア沿海州ではチョールタヴィ‐ヴフロータ洞穴以外にも数例の類例が知られている。
まだ、厳密な年代などを比較しないといけないが、仮に日本列島の玖状耳飾が大陸起源の可能性が高いとすれぱ、現段階ではその発生段階では北方からの影響が大きかったと考えている。
ただし、玦状耳飾などの縄文時代前期から中期にかけての石製装身具セットはさらに多様に発展しており、前期後葉に出現する「の」字状石製品(垂飾)のように北方の影響とだけでは理解できないものも存在しており、従来から指摘する江南地方などの影響も検討していかなければならないだろう。
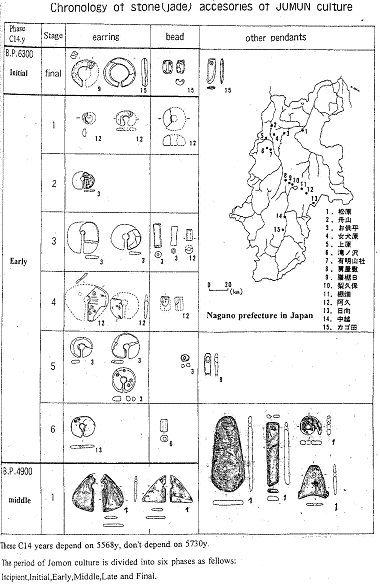
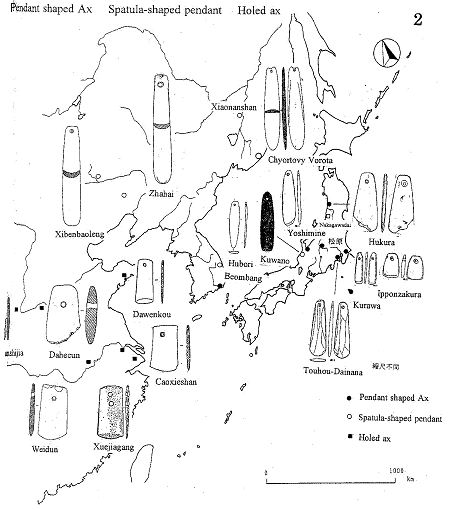

●縄文人渡海交流を示す三点セット
○玦状耳飾(けつじょう・みみかざり)玦状とはローマ字のCのような一部が欠けた円環型を言う。
○管玉(かんぎょく)
○箆状垂飾(へらじょう・すいしょく)
玉で作られた中国東北地方の玦状耳飾
信州で見つかった玉
三内丸山遺跡の玉製のへら状垂飾
この三つの遺物が日本の三内丸山遺跡、そして中国内モンゴル区などの興隆窪文化の遺跡から出てくる。それは両者間の、今からだいたい6000年前以降からの、深い交流を指し示す遺物であるとされる。
●興隆窪文化
「興隆窪文化(こうりゅうわ-ぶんか)は中華人民共和国内モンゴル自治区から遼寧省にかけて紀元前6200年頃-紀元前5400年頃に存在した新石器時代。紅山文化に先行する遼河流域の文明(遼河文明)のひとつとされる。
興隆窪文化は、ヒスイなどの玉製品(玦 : けつ)の出土する文化としては中国最古のものであり、なおかつ龍の出現する文化としても中国最古のものである。また興隆窪文化の遺跡からは平底円筒状の、比較的低い温度で焼いた土器(陶器)が出土する[1]。黄河文明のほかに、先史中国の新石器文化が南の長江流域および北の遼河から発見されているが、興隆窪文化は遼河文明の一つとして重要である。
興隆窪文化の遺跡においては、集落が計画的に築かれた痕跡も見られる。住居が列をなしている状態が3つの遺跡から発見された。またいくつかの遺跡ではひときわ大きな建物が発見されたほか、堀に囲まれた環濠集落も見つかっている。」
三内丸山と、対面する緯度にある中国東北地方との縄文中・後期の交流は、これまで円筒土器や玦状耳飾の一致から言われてきていた。しかしそれだけでは弱いと考えていた川崎は、あらたに箆状垂飾という決定打を発見。管玉とあわせて「三点セット」だと論じた。つまりこれらによって日本の縄文人にはすでに、日本海を横断する船舶と、その能力があったことは確実になった。
これにさらに円筒土器もあわせてより確実視するのが上垣外憲一である。
「中国東北部では、日本の縄文時代早期に相当する時期くらいに円筒土器が出現する。三内丸山遺跡は円筒土器文化の拠点的集落跡であるが、よく似た形の土器が中国東北部の狩猟採集文化の遺跡から大量に見つかっている。形が似ているだけでなく、文様のつけかた、区分、容量までよく似ている。」上垣外『ハイブリッド日本』第三章70p
7000年前の興隆窪文化の円筒土器
6000年前 三内丸山の円筒土器
少なくとも7000年前には、日本の東北や日本海沿岸の縄文文化と、中国東北部の文化とは舟でつながっていたと二人は明確に考えている。
そのためには、両者には共通言語があったはずである。東アジアエスペラントともいうべき言語である。
それは朝鮮半島南部の海岸部倭族と対岸の対馬・壱岐・隠岐・玄界灘沿岸・日本海沿岸の弥生人の間にも、当然あったはずである。貿易用共通言語、共通単語である。それを上垣外は倭人の「リンガ・フランカ」=共有言語であると言っている。
次回そのリンガ・フランカとは?
ここから日本語と朝鮮語の共通起原を、今回はるかにまさぐってみたい。
共通したトルコ地域のテュルク系膠着言語から両者がいつ分岐したのか?
どこでまったく異なった発音を持っていくようになるのか?
弥生人の言葉と縄文人の言葉は、いったいどうやって日本語へ変化していったのか?
Kawakatu’s HP 渡来と海人http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/
かわかつワールド!なんでも拾い上げ雑記帳
http://blogs.yahoo.co.jp/hgnicolboy/MYBLOG/yblog.html
画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/
Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html
公開ファイルhttp://yahoo.jp/box/6aSHnc
装飾古墳画像コレクションhttp://yahoo.jp/box/DfCQJ3
ビデオクリップhttp://www.youtube.com/my_videos?o=U
かわかつワールド!なんでも拾い上げ雑記帳
http://blogs.yahoo.co.jp/hgnicolboy/MYBLOG/yblog.html
画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/
Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html
公開ファイルhttp://yahoo.jp/box/6aSHnc
装飾古墳画像コレクションhttp://yahoo.jp/box/DfCQJ3
ビデオクリップhttp://www.youtube.com/my_videos?o=U